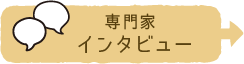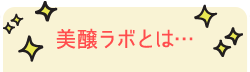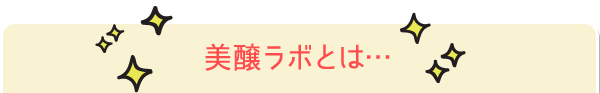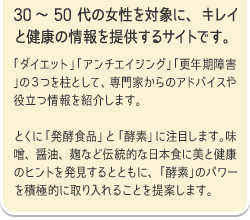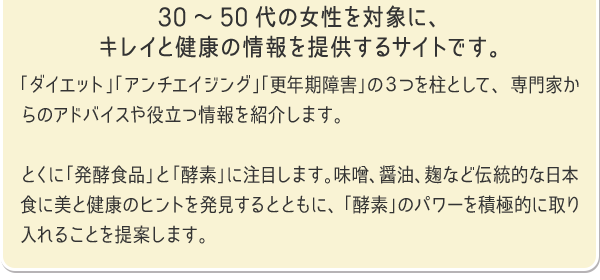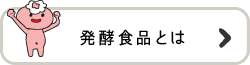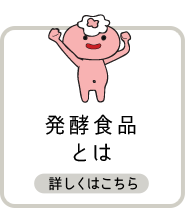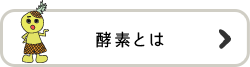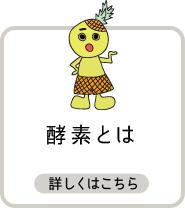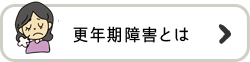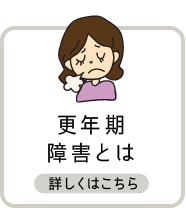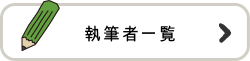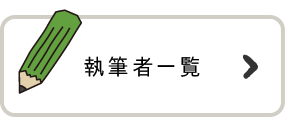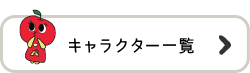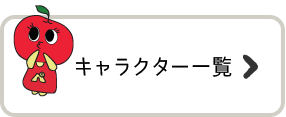「なすのぬか漬けをきれいな紫色のまま作るコツはあるのかしら……」
「ジューシーでおいしい自家製のなすのぬか漬けを作ってみたい!」
なすのぬか漬けは、そのみずみずしさや柔らかい食感、きれいな紫色が特徴で、とてもおいしく人気があります。
そんな魅力がたくさんある、なすのぬか漬けを作ってみたい、そう思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、3人の子育て中の薬剤師・薬膳アドバイザーが、なすのぬか漬けの漬け方をご紹介します。
なすのぬか漬けは、なすから溢れ出るジューシーな水分がとてもおいしく、子どもたちも大好きです。
浅く漬けてもしっかり漬けても、それぞれその風味が味わえます。
なすそのままの鮮やかな紫色を保って漬けると、その出来上がりに感動しますよ!
色素を保つ方法もしっかりご紹介するので、ぜひ試してみてくださいね。
スーパーで一年中手に入りやすいなすを、自分好みのぬか漬けにして楽しみましょう!
目次
ぬか漬けでもなすの紫色を残すには?

なすのぬか漬けは鮮やかな紫色のまま漬けたいですよね。
紫色の鮮やかさを保つためにはいくつかの方法があります。
ここでは、色落ちを防ぐための代表的な3つをご紹介します。
どれも簡単にできるので、お好みの方法を試してください。
なすを塩で揉んでから漬ける
なすのぬか漬けを作る前に、塩でなすを揉む方法です。
これにより、なすから水分や苦味を取り除くことができます。
水分を抜くことで色落ちを抑える効果がありますよ。
鉄粉入りのぬか床を使う
ぬか床に鉄粉を混ぜることで、色素の分解を防ぐ効果があります。
鉄粉が色素を安定させるため、美しい紫色を保つことができるでしょう。
ぬか床用の鉄なすを入れる
鉄分を多く含む鉄なすは、南部鉄器で作られた漬物用の鉄製品です。
ネットやスーパーなどで販売されています。
ぬか床に加えることで、色素の酸化を防ぎ鮮やかな紫色を保つのに役立ちますよ。
オススメ記事
発酵食品の効果的な食べ方とは|免疫力を高めて腸内環境を整える摂取法
発酵食品は効果的に食べる方法があるんです。あなたの悩みに合わせて現役看護師がおすすめな発酵食品を選んでみました。より効果的な食べ方を知って、あなたの健康増進のヒントを見つけてくださいね。簡単なレシピもご紹介します。

なすのぬか漬け

材料(2人前)
- なす
- 4本
- 塩
- 適量
- ぬか床
- 300g程度
なすのぬか漬け:手順

- なすをよく水洗いし、水気を拭き取ります。
- なすのヘタの真ん中に切り込みを入れて、ヘタの部分を取り除きます。
- なすを縦半分に切ります。太いなすの場合は4等分に切りましょう。
- なすの切り込みの間にぬか床を入れながら漬けていきます。ぬかをしっかりとなすに詰め込むようにします。
- 4を密閉容器に入れた状態で、冷蔵庫で保存します。
【漬ける時間】
なすのぬか漬けで漬ける際の適切な時間は、ぬか床の状態によって異なります。以下がその目安です。
- 常温のぬか床の場合:半日~1日
- 冷蔵保存の場合:常温の2~3倍の漬け時間が必要(2〜3日程度)
【注意点】
- 常温でも冷蔵庫でも漬け時間は、なすの大きさや厚みによって変わります。
- 漬け過ぎるとなすの風味が落ちる可能性があるので、味見をして好みの漬け具合を見極めましょう。
ぬか漬けの美味しい保管方法

なすのぬか漬けはぬか床から取り出した瞬間から、色の変化が始まります。
そのため、なすの紫色の美しい色を保つためには、なるべく早く食べることがおすすめです。
ぬか床から出したらすぐに食べましょう。
ただし、色が茶色く変化してしまっても問題なく食べられます。
冷蔵庫で2〜3日間の保存が可能です。
長時間放置すると、色だけでなく風味も変化してしまうので、おいしさを損なわないためにも早めに使い切りましょう。
一方で、なすのぬか漬けの冷凍はおすすめしません。
冷凍することで香りや食感が損なわれる可能性があります。
なすをぬか漬けする嬉しい効果とは?

なすをぬか漬けにすることで、多くの栄養素が増加します。
その栄養素は健康に良い影響をもたらすでしょう。
以下で、その代表的な効果をご紹介します。
健康効果
なすに含まれる水溶性食物繊維は、善玉菌の増加を促します。
腸内環境を整えることで便秘の改善に役立つでしょう。
ミネラル補給
ぬかには塩が含まれており、なすをぬか漬けにすることでナトリウムを摂取することができます。
ナトリウムは筋肉の正常な動きをサポートし、けいれんや不整脈を予防する効果があります。
ビタミン摂取
なすにはビタミンB1、ナイアシン、ビタミンB6、パントテン酸、ビタミンCなどが含まれています。
ぬか漬けのなすを食べると、これらのビタミンを摂取することが可能です。
エネルギー代謝の促進や免疫力の向上、肌の健康維持などに役立ちます。
なすのぬか漬けアレンジレシピ
なすのぬか漬けは、そのままでももちろん、みずみずしくジューシーでおいしいですが、アレンジすると新しい味を楽しむことできます。
少し漬けすぎてしまったしまったり、色が鮮やかにならなかったりした場合にもおすすめです。
さっぱり!なすときゅうりのぬか漬け冷や汁

なすのぬか漬けときゅうりのぬか漬けなど、ぬか漬けを使った冷や汁のレシピです。
刻んだぬか漬けを加えるだけで、ぬか漬けの風味の良さが冷や汁に加わり、とても慈悲深い味わいになります。
冷や汁なので冷たいまま食べるレシピですが、温めてもおいしく食べられますよ。
【調理時間】
10分程度
材料
- なすのぬか漬け
- 適量
- きゅうりのぬか漬けなど
- 適量
- だし
- 500ml
- 醤油
- 大さじ2
- 味噌
- 大さじ1
- みりん
- 大さじ1
- 塩
- 少々
- おろししょうが
- 小さじ1
- ごま
- 適量
- 青ねぎ(みじん切り)
- 適量
【作り方】
- なすのぬか漬け、きゅうりのぬか漬けなどは、薄めに切ります。
- ボウルにだしを入れ、醤油、味噌、みりんを加えてよく混ぜ、味を調えます。
- 2に1を入れ、ぬか漬けの塩気に合わせ、塩で味を調整します。
- おろししょうがを加えます。
- 器に盛り、ごまと青ねぎを乗せてできあがりです。
オススメ記事
酵素を食品から摂取する効果的な方法とは?おすすめ発酵食品レシピも紹介
酵素をたっぷり含んだ食品を食べることで、健康や美容に最大限活かしましょう。何の食品を、どのように食べれば酵素摂取に効率的なのか徹底的にご説明。また、今日からでも作れるような簡単レシピもご紹介します。

なすのぬか漬けを食卓に添えて◎

なすのぬか漬けは、おいしさと健康が融合した贅沢な料理です。
ぬか床で発酵させることによって、独特の風味を楽しむことができます。
漬ける時間も楽しんで待つことができるでしょう。
味見をして、お好みの風味になったら取り出してくださいね。
鮮やかな紫色を保つのも、なすのぬか漬けを作る際の大きなポイントです。
色味を保つ方法は、簡単なのでぜひ試してみてください。
紫色が食卓にあるだけで、料理全体が鮮やかに見えますよ。
なすのぬか漬けを作って、その色鮮やかな魅力と口に広がる深い味わいを堪能しましょう。