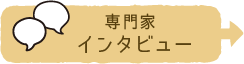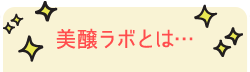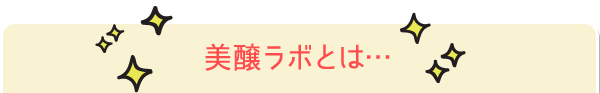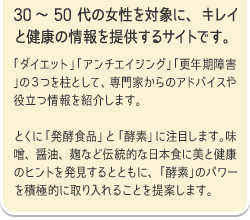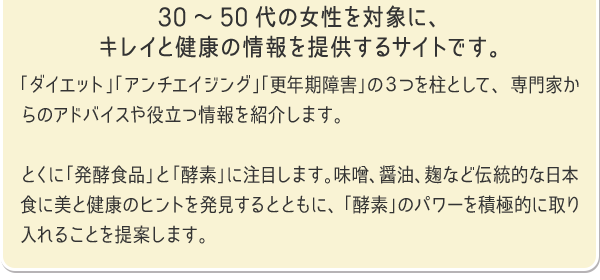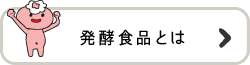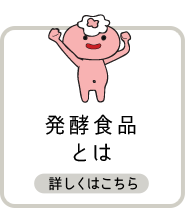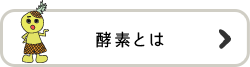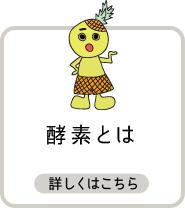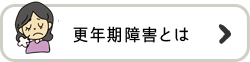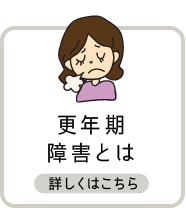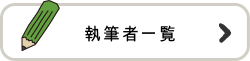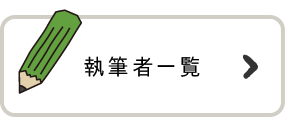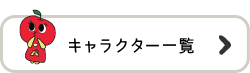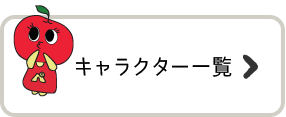「ぬか漬けを作ってみたいけど、どうやって作るの?」
「ぬか床作りってなんか難しそう……。」
「ぬか床の作り方を知りたい!」
発酵食品で、独特の酸味があるぬか漬けを、家で手作りしてみたいですよね。
自家製のぬか漬けを作るためには、「ぬか床」を仕込む必要があります。
ぬか床の仕込みをきちんと手順を踏んで行うことが、美味しいぬか漬けにつながりますよ。
この記事では、自家製のぬか漬けの作り方を知りたい方へ、ぬか床の作り方や準備するもの、お手入れ方法などを解説します。
ぬか床を作るのに少し時間はかかりますが、初心者の方でも簡単にできる作り方ですので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
ぬか床作りに必要なもの

ぬか床の作り方を説明する前に、必要な材料と道具をご紹介します。
必要な材料
- 生ぬか
- 1kg
- ミネラルウォーター
- 1L
- 粗塩(自然塩が望ましい)
- 130〜150g
- 昆布
- 5cm四方を2~3枚ほど
- かつお節
- 2g
- 鷹の爪
- 2本(ちぎっておく)
- (煮干し)
- 5匹分
- (干し椎茸)
- 少々
- (茹で実山椒)
- 少々
- 捨て漬け野菜
- 適量(キャベツの外葉、野菜の皮など)
※()内の材料はお好みで用意してください。
米ぬかは、できればお米屋さんで鮮度の良いものを選びましょう。
昆布とかつお節は、ぬか床にうま味をプラスし、鷹の爪は防腐のためなので、ぜひ入れておきたいものです。
必須ではないものの、煮干しや干しシイタケもうま味をプラスし、茹でた実山椒は香りづけになりますので、可能であればいれてみましょう。
必要な道具
- 蓋つきの食品用保存容器(約3~4L)
- 大きめのボウル
保存容器は蓋つきでしっかり密閉できるものを選びましょう。
大きさは今回の分量で作る場合は、容量がおよそ3〜4Lが望ましいです。
容量が小さい保存容器だと、ぬか床を混ぜにくかったり、ぬか床がこぼれてしまったりします。
また、保存容器はプラスチック製でも構いませんが、ホーロー製であれば、ぬかのにおいが移りません。においが気になる方にはホーロー製がおすすめです。
ぬか床専用のホーロー容器なども販売されていますので、それを使用するのも良いでしょう。
ぬか床の作り方の手順

必要な材料と道具が揃ったら、いよいよぬか床の作り方を説明します。
ぬか床の作り方のステップとしては、「材料を混ぜる」「捨て漬け」の2つがあります。
ステップごとに作り方を解説していきます。
ステップ① 材料を混ぜる
- 生ぬかと粗塩を、ボウルに入れて混ぜる。
ある程度混ざったら、ミネラルウォーターを900mlほど加えて良くかき混ぜる(ミネラルウォーターは100ml残しておく)。手でしっかりと均一になるよう、味噌くらいの硬さになるまで混ぜ、硬いようであればミネラルウォーターを足して調整する。 - ぬか床のもとが出来上がったら、かつお節と鷹の爪(あれば干し椎茸・実山椒)を加え、よく混ぜる。
- ぬか床のもとを保存容器に移す。
ポイントは、ぬか床のもとを手でぎゅっと握った時に、少し水分がにじむくらいを目安に硬さ調整をすることです。
ステップ② 捨て漬け
- 捨て漬け野菜をステップ①で作ったぬか床に埋めるように入れ、表面を平らにする。(今回の分量だと、キャベツの葉1〜2枚分)さらに昆布と煮干しをぬか床に挿すようにして埋める。
- ぬか床を手のひらでぎゅっと空気を抜くように押し付け、蓋をして密閉する。
- 捨て漬け野菜を入れてから初めの10日間は1日2回、ぬか床をしっかり底からかき混ぜ、次の10日間は1日1回同様にかき混ぜる。
捨て漬け野菜を入れてから4〜5日経ったら、古い捨て漬け野菜は捨て、新しい捨て漬け野菜を埋める。 - 捨て漬け期間は約2週間行い、ぬか床から酸味のある香りがしたり、ふかふかとした触り心地であったりすれば完成。
捨て漬け野菜を入れ替える際、漬けた後の捨て漬け野菜のぬかはこそげ落とし、野菜の水分をぎゅっと絞って、ぬか床に戻してあげましょう。
捨て漬けに使った野菜は食べられる状態ではないので、そのまま処分します。
オススメ記事
発酵食品を摂りすぎるとどうなるの?失敗しない1日の摂取量とデメリット
発酵食品を摂りすぎると体調不良になる?そうならないために、発酵食品適切な摂取量と効果を解説します。摂り過ぎるとお腹の不調やむくみ、高血圧、高血糖のリスクの原因に。バランスのとれた食生活を送るための献立もご紹介します。

ぬか床を作った後に最初にやるべきこと「捨て漬け」とは?

「捨て漬け」は文字通り、野菜を漬けて捨てることで、キャベツの外葉や芯、にんじんの皮などの野菜くずをぬか床に入れて漬けます。
捨て漬けの野菜が、ぬか床に含まれる菌のエサになったり、ぬか床に水分を与えたりする役割があり、ぬか床の熟成をさせます。
もし、捨て漬けをせずに野菜を漬けると、ぬか漬け本来の風味や香りが味わえません。
ぬか床を育てるためにも、捨て漬けの作業は必須ですので、焦らず根気よく捨て漬けを繰り返しましょう。
ぬか床の毎日のお手入れ方法

ぬか床は、1日に1回、表面と底を入れ替えるように手でしっかりとかき混ぜましょう。
混ぜずにそのまま放置しておくと、一部の菌が過剰に発酵し、ぬか床中の菌のバランスが崩壊し、味や風味が落ちたり、異臭がしたりします。
毎日かき混ぜて、ぬか床表面の菌と底の菌を入れ替えることで、ぬか床に存在する菌のバランスが保たれ、美味しいぬか漬けができます。
ぬか床の保管方法や温度管理はどうすればいい?
ぬか床を良い状態に保つためにも、保管方法や温度管理も重要です。
ぬか床に適している温度は20〜25℃と言われているため、基本的に常温での保管が可能です。
しかし気温が高い夏場だと、ぬか床中の菌が異常発酵し、酸味が強くなったり、カビが生えたりします。そのため、夏の間は冷蔵庫での保存がおすすめですよ。
ぬか床を温度の低い冷蔵庫で保管すると、菌の発酵スピードがゆっくりになり、野菜が漬かる時間が長くなります。
漬け時間は調整するようにしましょう。
ぬか床に何か白いものが出てきた!どう対処すべき?
ぬか床を「しっかりかき混ぜていない」「しばらく混ぜ忘れた」といった場合、表面に白いものが出てくる場合があります。
この白いものの正体は酵母の一種で、摂取しても体に悪影響はありませんが、ぬか漬けにした時の味が変わってしまいます。
白いものが表面に現れてしまった際は、周りにあるぬかごと白いものを取り除き、良くかき混ぜましょう。
ぬか床を管理する上でのちょっとした裏技
ぬか床を混ぜる際は、きれいに洗った素手でかき混ぜてもかまいませんが、塩分が濃いため、人によっては手荒れしてしまう場合があります。
手荒れ予防のためにもビニール手袋をして混ぜてもかまいません。
オススメ記事
【古漬けの食べ方・作り方】漬けすぎたしょっぱいぬか漬けの美味しい魅力
「ぬか漬けが浸かりすぎてしまったけれど、これは食べられるのかしら!?」そんなお悩みに対して、古漬けをご紹介します。この記事では、3人の子育て中のママ薬剤師・薬膳アドバイザーが、古漬けの魅力を最大限に引き出すためのおいしい食べ方や作り方、塩抜きの方法やアレンジレシピまで幅広く説明します。

ぬか床をつくって楽しい発酵食品生活を◎
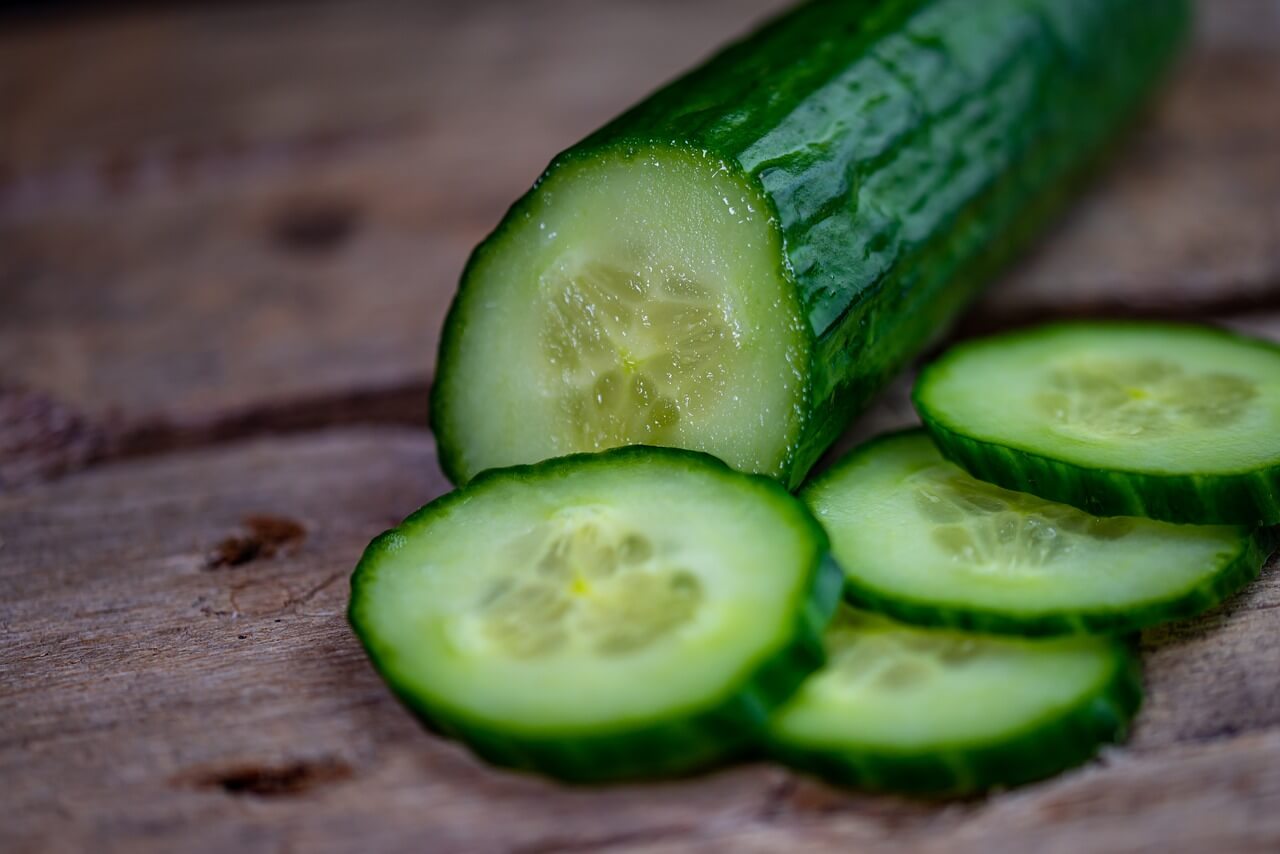
今回は、自家製のぬか漬けを作りたいあなたに、ぬか床の作り方や必要な準備物を中心に解説をしました。
作り方は意外とシンプルですので、初心者でも簡単にできますよ。
ぬか漬けを作れる状態にするまでは、少し時間がかかるぬか床作りですが、作ってお手入れをきちんとすれば、美味しい自家製のぬか漬けができます。
ぜひこの記事のぬか床の作り方を参考にして、ぬか漬け作りを楽しんでみてくださいね。