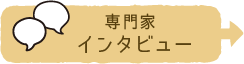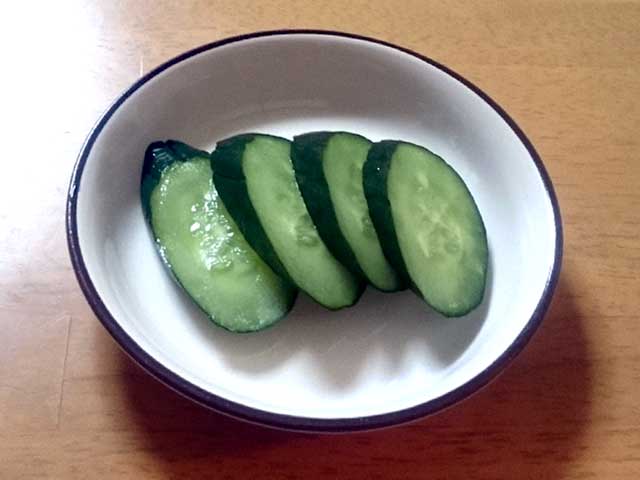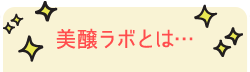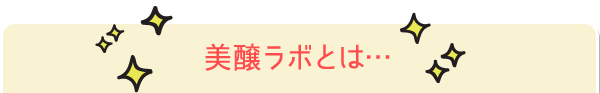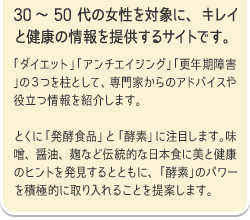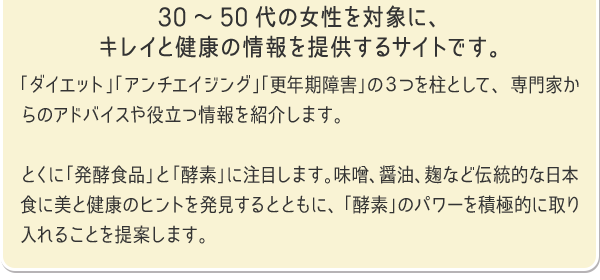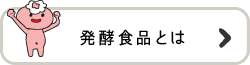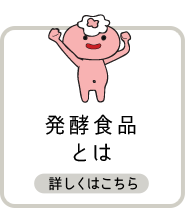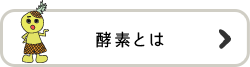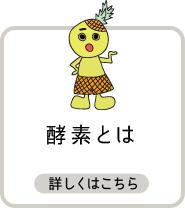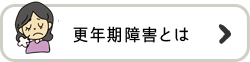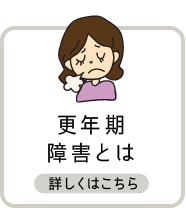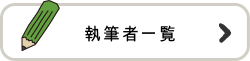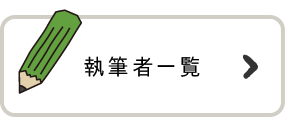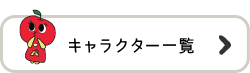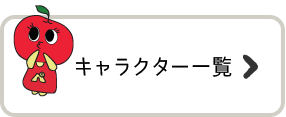きゅうりのぬか漬けはとても歯ごたえがいいですし、好きな人も多いのではないでしょうか? でも、お店で販売されているきゅうりのぬか漬けって「化学調味料」が入っているものが多いんですよね……。
そんなときは、自分で漬けてしまいましょう! 市販とは比べ物にならないくらい美味しいですし、無添加なのでお子さんにも安心して食べさせてあげられますよ。
自分で漬けると減塩にも
きゅうりのぬか漬けって結構塩辛いですよね。だから、食べるときに塩分が気になる人も多いのではないでしょうか? ちなみに、きゅうりのぬか漬けの塩分は「100gあたり約5.3g」ほど。(漬け時間で変わったりもするので一概には言えませんが)ちょっと高いですよね。
ですが、きゅうりには塩分を体の外に排出する「カリウム」が含まれているので、大量に食べなければ何の問題もありません。ですが、市販のぬか漬けは別です……。塩分以外に「ぬか漬けのうま味」なども化学調味料で味付けられているので、塩分もかなり高めになります。そうなると、塩分を排出しきれなくなってしまいます。
きゅうりをぬか漬けにすると「ダイエット」にも
きゅうりには栄養がないと言われていますが、栄養素自体はバランスよく持っています。ただ、量がものすごく少ないだけなんですよね……。でも、ぬか漬けにするとぬかの栄養を吸収するので栄養の量がアップします。
脂肪を燃焼させるビタミンB2、糖質の代謝を助けるビタミンB1など。しかも、きゅうりには脂肪を分解する「ホスホリパーゼ」という酵素が含まれているので、ぬか漬けにすることでそのまま食べるよりもダイエットの手助けになりますよ。
では、そんなきゅうりのぬか漬けですがどうやって漬けたらいいのでしょう?
とっても簡単!きゅうりの漬け方とは?
【材料】
・ぬか床
・きゅうり
・塩

【漬け方】
1. きゅうりを流水で洗って、水気を拭いておく
2. きゅうりに天然塩(小さじ1)をふりかけ、塩もみをする

3. ぬか床に漬けていく

4. 常温で真夏なら4時間、真冬なら1日漬ける
(冷蔵庫内で漬けるなら1日でOK)
5. 漬かったきゅうりは、水でぬかを落として水を拭き取る
6. 好みの大きさに切って食べてください
きゅうりのぬか漬けは、漬け時間を見ながらぬか床の状態も確認できるのでおススメなんですよね。常温でぬか床を保存している場合、特に夏場(30度以上になる場所で)はぬか床の塩分が少ないと発酵しすぎたり、雑菌がわいたりしやすくなります。なので、暑い時期もしくは暑くなる部屋で保存するときは「きゅうりが4時間で漬かるくらいの塩分濃度」にしておけば、ぬか床がおかしくなることも防ぐことができますよ。
保存方法と保存期間
取り出してその日のうちに食べるのが一番美味しいですが、つい漬けすぎることもあるでしょう。そんなときは、ぬかをつけたままラップで包み、野菜室で保存します。(野菜室のほうが冷蔵庫より温度が低いですからね)そして3日以内に食べるようにしてください。でないと、だんだん塩辛くなってしまいますよ。
もしも漬かりすぎてしまったら……
きゅうりのぬか漬けを美味しく食べるなら、もちろんそのままが一番です。でも、たまに漬かりすぎてしまうこともあるでしょう。そんなときは、塩抜き(水に一定時間入れておく)もいいですが、納豆パスタにしても美味しいですよ。
納豆パスタ

【作り方】
1. ゆでたパスタに付属のタレを混ぜた納豆を入れる
2. 漬かりすぎたきゅうりを細かく切って、2に入れる
3. よく混ぜて食べる
まとめ
・きゅうりは最初に塩もみをしてから漬ける
・きゅうりの漬かり時間をぬか床の塩分調節の目安にする(とくに夏場)
きゅうりやぬか床に使う塩ですが、こだわるなら「天然塩」がおすすめですよ。血圧を下げるミネラルも摂れますしね。私は一時期使っていたんですがお値段も結構するので、今は「再生加工塩(外国の天然塩を海水に溶かしてもう一度結晶化したもの)」を使っています。
ちなみに、天然塩の見分け方は塩づくりの工程が「天日・平窯」になっているもの。気になる方はチェックしてみては?