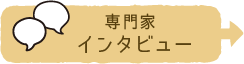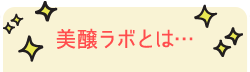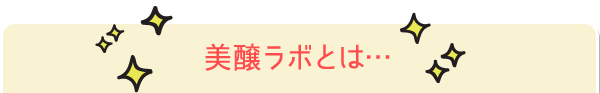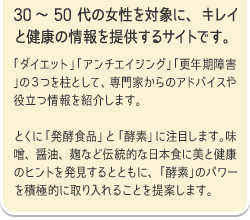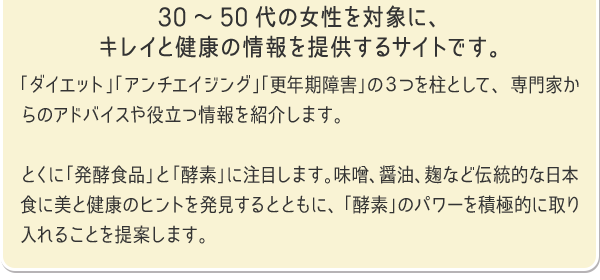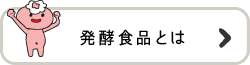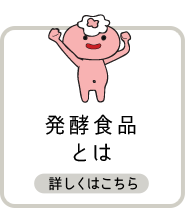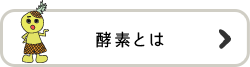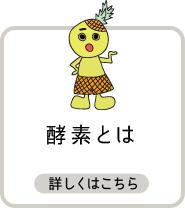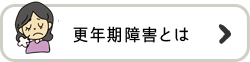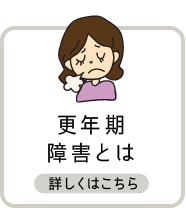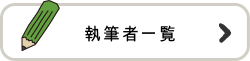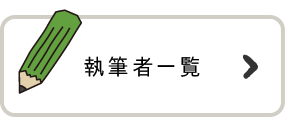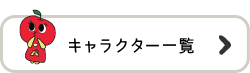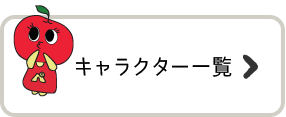高い健康効果が注目されている酵素玄米。
圧力鍋を使えば家庭で作れますが、実践する前に詳しい作り方や失敗しないポイントを知っておきたいですよね。
この記事では、食によって体の中から健康維持に努めている管理栄養士が、圧力鍋を使った酵素玄米の作り方をご紹介します。
酵素玄米の保存方法や、酵素玄米についてよくある疑問にもお答えするので、この記事を参考にしておいしい酵素玄米作りにチャレンジしてください。
目次
酵素玄米と精白米の違い

酵素玄米と精白米の違いは、以下のとおりです。
| 酵素玄米 | 精白米 | |
|---|---|---|
| 原材料 | 玄米、小豆、塩 | 米 |
| 見た目 | 赤飯のような赤色 | つやのある白色 |
| 香り | 玄米特有の香りは控えめ | ふくよかな香り |
| 食感 | もちもちして弾力がある | 適度な粘りがある |
| 味 | ほんのり甘みと塩味がある | やさしい甘みがある |
| 栄養価 | 高い | 普通 |
酵素玄米とは、玄米・小豆・塩を混ぜ合わせて炊飯し、3日間ほど保温して熟成させた玄米ご飯のことです。
酵素玄米の特徴は、熟成させることで生じる独特の食感や甘みのある味わいです。
一般的な玄米ご飯は食感がパサパサしている、玄米特有の青臭い香りがする、消化不良を起こすことがある、といったデメリットがあります。
しかし酵素玄米はこれらの問題が解消されており、食べやすいことで人気が高まっています。
酵素玄米と精白米の大きな違いは、見た目です。
酵素玄米は小豆と塩を加えて作るため、赤飯に近い見た目や味わいになります。
さらに、食感にも違いがあります。精白米よりも、もっちりした食感が楽しめる酵素玄米のほうが好き、という人は少なくありません。
酵素玄米と精白米の栄養価の違いにも注目してください。
玄米から胚芽やぬかを取り除くと、精白米になります。
この胚芽やぬかには、ビタミンや食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。
栄養価の高い主食を食べるなら、精白米よりも、玄米を使用した酵素玄米がおすすめです。
酵素玄米の圧力鍋を使った炊き方

おいしくて栄養価が高い酵素玄米を、実際に作ってみましょう。
ここからは、圧力鍋を使った酵素玄米の作り方を詳しく紹介します。
分量の目安
圧力鍋の容量により、材料の分量は異なります。
以下の表を参考にしてください。
| 圧力鍋の容量 | 2.0L | 2.5L | 3.0L | 3.5L |
|---|---|---|---|---|
| 玄米 | 2合(300g) | 3合(450g) | 4合(600g) | 5合(750g) |
| 小豆 | 20g | 3g | 4g | 50g |
| 塩 | 2g | 3g | 4g | 5g |
| 水 | 540cc | 810cc | 1080cc | 1350cc |
必要な器具

圧力鍋で酵素玄米を作るときに必要な器具は、以下のとおりです。
- 圧力鍋
- 保温ジャー
- ザル
- しゃもじ
酵素玄米を作るには保温する工程が必須ですが、圧力鍋には保温機能がありません。
圧力鍋で酵素玄米をつくるときには、必ず保温ジャーを用意するようにしてください。
玄米を洗うときに泡立て器でかき混ぜると、玄米の表面に傷がついて水が浸み込みやすくなります。
玄米が水をよく吸って、よりパサつきの少ないもっちりした食感になるため、酵素玄米をおいしく作るなら泡立て器も用意するとよいでしょう。
作り方
圧力鍋を使った酵素玄米の作り方を紹介します。
以下は玄米を3合炊く場合の作り方なので、加圧時間などは玄米の量によって調整してください。
- 玄米と小豆を合わせて、水を変えながら3〜4回洗う。ザルに上げて水気を切る。
- 圧力鍋に移し、分量の水と塩を加えてかき混ぜ、塩を溶かす。
- 1時間ほど浸水させてから、圧力鍋を火にかけて加圧する。圧力がかかったら、弱火にして15分ほど加圧する。

- 火を止めて、圧力が抜けるまで置いて蒸らす。ふたを開けてしゃもじで一度軽く混ぜ、温めた保温ジャーに移す。
- 1日1回は全体を返すようにしゃもじで混ぜながら、保温ジャーで3日間熟成させる。

炊飯器で酵素玄米を炊くと、浸水に6時間以上かかってしまいます。
しかし圧力鍋を使うと浸水時間が短くて済むうえに、炊飯時間も長くかかりません。
④で炊けた酵素玄米はすぐにでも食べられますが、色は薄く、もっちりした食感も少ないはず。
酵素玄米ならではの味や食感を楽しむなら、3日間は保温するようにしてください。
保存方法・保存期間

保温ジャーで3日間ほど熟成した酵素玄米は、冷凍保存することをおすすめします。
保温ジャーに5日間以上入れておくと、乾燥したり食感が悪くなったりして、おいしく食べられなくなる可能性があるためです。
冷凍する場合は、広げたラップの上に酵素玄米をのせて平らにならし、ラップでぴっちりと包みます。
粗熱が取れたら冷凍庫に入れましょう。食べるときは、電子レンジで解凍してください。冷凍した酵素玄米の保存期間は約1ヶ月です。
酵素玄米についてよくある疑問点

酵素玄米については、さまざまな噂が飛び交っています。
そこで、酵素玄米の気になる疑問点について回答します。
Q1:酵素玄米に毒があるってほんと?
酵素玄米の材料となる玄米には毒がある、という噂を耳にしたことがあるかもしれません。
この毒は、玄米の成分「フィチン酸」と「アブシジン酸」を指していると考えられます。
結論からいうと、玄米に含まれるフィチン酸とアブシジン酸に毒性はありません。
フィチン酸に毒があるといわれているのは、フィチン酸はミネラルと結合しやすく、体内でのミネラルの吸収を妨げるためです。
しかしフィチン酸の安全性は実験で証明されています。
むしろ、フィチン酸は強力な抗酸化作用や血栓を予防する効果、尿路結石や腎結石の予防効果が期待されるとして研究が進められている成分なのです。
アブシジン酸は植物ホルモンの一種であり、人の細胞内にあるミトコンドリアを傷つける、とされています。
しかしアブシジン酸についても安全性が確認されており、危険性よりも、抗炎症作用による動脈硬化や糖尿病の予防効果が注目されています。
Q2:酵素玄米を食べると痩せる?

酵素玄米そのものに痩せる作用はありませんが、酵素玄米は食後の血糖値の上昇を緩やかにするため、太りにくい食品であると考えられています。
食事で糖質を摂取すると、血液中に含まれる糖質の量を示す「血糖値」が上がります。
この血糖値を下げるのは「インスリン」というホルモンの役割です。
インスリンは血糖を脂肪に変えて、体に蓄えることで血糖値を下げています。
食後に血糖値が急上昇すると、インスリンが大量に分泌されてしまいます。
多くの糖質が体脂肪に変わるため、太りやすくなるのです。
酵素玄米の材料である玄米と小豆は、食後の血糖値の上昇をおさえる作用があります。
そのため酵素玄米を食べると血糖値の上昇が緩やかになり、体に脂肪がつきにくくなると考えられます。
Q3:酵素玄米のデメリットって?
酵素玄米のデメリットは、作るのに時間がかかることと、一般的な白ご飯や玄米ご飯よりも食中毒のリスクが高いことです。
酵素玄米は、炊いてから3日間の保温熟成が欠かせません。
毎日酵素玄米を食べたい場合は、酵素玄米の熟成中に食べる分を確保する必要があります。
計画を立てて、酵素玄米を作りましょう。
酵素玄米が衛生的に取り扱われて、適切な温度で保温されていれば、食中毒のリスクはおさえられます。
しかし不衛生なしゃもじでかき混ぜたり、保温温度が低かったりすると、食中毒菌が繁殖してしまうでしょう。
酵素玄米を作るときはきれいな調理器具を使用し、保温温度が下がりすぎないように注意してください。
Q4:酵素玄米を食べると便秘になるの?

食物繊維が豊富に含まれているため、便通を整えて便秘を解消する効果があるとされている酵素玄米。
しかし中には、酵素玄米を食べても便秘が治らない、便秘になったという方もいます。
酵素玄米を食べて便秘になった方は、すでに酵素玄米以外で十分な量の食物繊維を摂っているのかもしれません。
食物繊維は摂りすぎると、腸で詰まって便秘を引き起こす可能性があるためです。
水分や油分の摂取不足も、便秘をまねきます。水分が不足すると便が硬くなり、排便が困難になります。
油分には腸内で便のすべりをよくする作用があるため、ダイエットなどで摂取エネルギーを制限している場合も、適度に油分を摂るように心掛けましょう。
酵素玄米を圧力鍋でおいしく作ってみよう

酵素玄米は、玄米・小豆・塩を一緒に炊き上げて、3日間ほど保温熟成させた玄米ご飯です。
精白米よりも栄養価が高く、もっちりとした食感や甘みがあっておいしいため、家庭で作る人も多くいます。
家庭で酵素玄米を作るなら、圧力鍋を使うのがおすすめです。
圧力鍋を使うと、米の浸水時間や炊飯時間を短縮できます。
ただし圧力鍋で酵素玄米を作るときは保温ジャーが必要であること、衛生的に取り扱うことに注意しましょう。
この記事でご紹介した、圧力鍋を使う酵素玄米の作り方を参考にして、生活においしい酵素玄米を取り入れてください。
【参考文献】
かわしま屋「酵素玄米の作り方|炊飯器でもちもちに炊き上げるコツ【管理栄養士監修】」
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究」
日本食品分析センター「フィチン酸について」
内閣府 食品安全委員会「米国環境保護庁(EPA)、植物調節剤、S-アブシジン酸の残留基準値設定免除に関する規則改定」
オススメ記事
【発酵食品で免疫力をUPさせよう!!】腸内環境も整う食事法とは?
免疫力UPに効果的な発酵食品の秘密を解明。腸内免疫の要、発酵の力で健康的な生活を送れるよう、管理栄養士が発酵食品の免疫力について詳しく解説します。腸内環境を整えるための食事法から腸活のポイントまで。発酵菌が免疫細胞を活性化させる仕組みもご説明します。