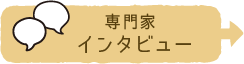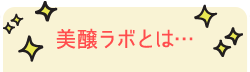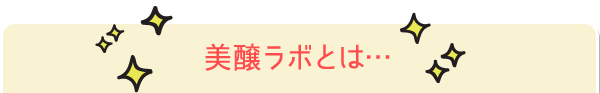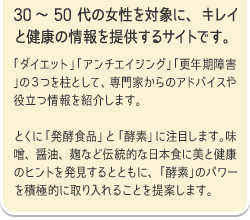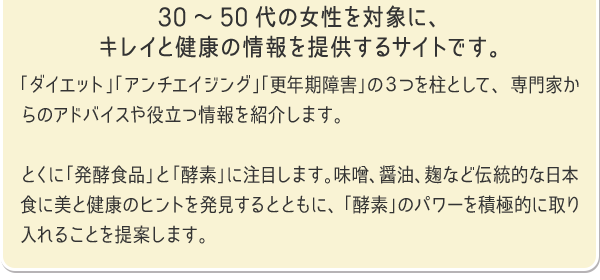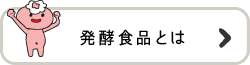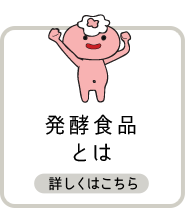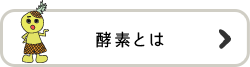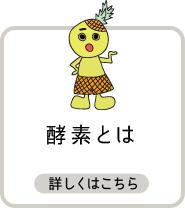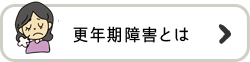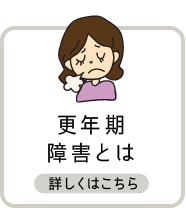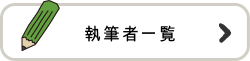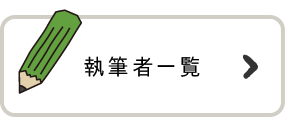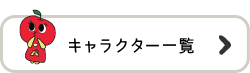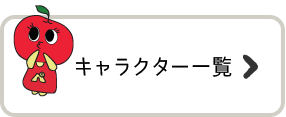発酵食品は健康面においてメリットがあるってわかっているけれど、摂りすぎて体調を崩さないか心配になりますよね。
特に、お腹を下したり、おならがたくさん出てしまうようなデメリットは誰だって避けたいものです。
今回は、看護師である筆者が発酵食品の適切な摂取量を注意点と共にお伝えします。発酵食品は食べ方や適切な量を守って取り入れれば、自分が健康になるサポートをしてくれます。
是非記事を読んで、発酵食品を日々の生活に取り入れる参考にしてみてください。
目次
発酵食品を摂りすぎるとどうなる?
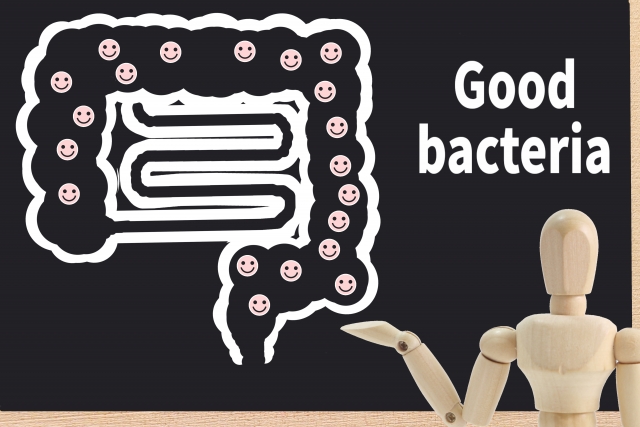
今回は発酵食品を食べすぎるとどんなデメリットがあるか、具体的にお伝えします。
おならがたくさん出るようになる、下痢になってしまう
ある研究結果によると、1日1人あたりのおならの平均回数は14〜23回と言われています。
おならの原因はいくつか挙げられますが、中でも食品に関してはFODMAP(フォッドマップ)というものがあります。
小腸で吸収されづらく、大腸で極度に発酵しやすい食べ物を指しています。
具体的な内容は F:発酵しやすい
O:オリゴ糖(豆、小麦など)
D:二糖類(牛乳、ヨーグルトなど)
M:単糖類(果物、蜂蜜など)
And
P:ポリオール(人工甘味料、カリフラワーなど)
であり、納豆やヨーグルトはこの食品群の中に含まれています。
FODMAP食品は腸の運動(腸ぜん動)を促進する働きがあります。
食べ過ぎると腸の運動が活発になりすぎるため、下痢や大量のガスが発生し、おならがたくさん出てしまうという結果になります。
むくみが出てくる
発酵食品の多くは塩分を多く含んでいます。食べすぎてしまうと、塩分過多となってしまいます。
体内の塩分濃度が高まってしまうと、体は濃度を薄めようとして、より多くの水を体に残すようになってしまいます。
大量に残された水は、心臓から遠い足先などへ運ばれてしまうと回収が難しくなってしまい、結果的にむくみとなってしまいます。
高血圧
むくみが起こる原因と同じであり、塩分過多となった体は、塩分濃度を下げようとたくさんの水を体に溜め込みます。
血圧とは、心臓が1回拍動するときに押し出す血液量と、血管の弾力によって決まります。水分が増えすぎた体の心臓に流れ込む血液量は、もちろん通常時よりも多くなっていますので、結果として血圧が上がってしまうのです。
高血糖
発酵食品の中には糖質を多く含んだものもあります。糖質を摂りすぎると、血液中のブドウ糖が増えすぎてしまいます。
余分なブドウ糖は肝臓に取り込まれますが、ブドウ糖が多くなりすぎると取り込みが追いつかず、血糖値は異常に高くなってしまいます。 これを「食後高血糖」といいます。
また、肝臓は過剰に増えたブドウ糖を取り込みきれないため、ブドウ糖は中性脂肪に変化し、脂肪組織として体内に蓄積され、結果として肥満にもつながってしまいます。
発酵食品を摂りすぎないための注意点

日々の生活で発酵食品を取り入れる際に、注意すべき点は「塩分量」と「糖分量」です。
発酵食品は、塩分を多く含むものがたくさんあります。
例えば、キムチや味噌、醤油などの塩分が高いものは食べすぎると、むくみや高血圧の原因となります。発酵食品を組み合わせた料理などをする場合には、どちらかは塩分の少ないものを使うことがおすすめです。
具体的には、味噌は減塩のものを使う、量を少なくして薄味を心がけるなどです。
薄味の料理はどうしても食欲が進まないという方は、味噌汁であればお出汁の量を多くして味噌の量を減らす、キムチであれば塩分量はそのままに唐辛子などを加えて辛さのみを足すなどすると、塩分を抑えたまま食べ応えのあるお食事となります。
またヨーグルトなどでは、糖分量に気をつけることも必要になってきます。
オススメ記事
発酵食品でアレルギー体質を改善できる?腸内環境を整えて毎日を元気に!
発酵食品は、実はアレルギー体質改善のカギになるのです。アレルギー症状を軽減する方法の一つは腸内環境を整えること。発酵食品は腸内のバランスを整え、健康的な生活をサポートしてくれます。管理栄養士が教える効果的な食品や簡単レシピも参考にしてください。

摂取の仕方に注意すれば大丈夫!発酵食品パワーとは

発酵食品は摂りすぎなければ多くのメリットがあります。
今回は発酵食品を食べることで得られる嬉しい効果をご紹介します。
ダイエット効果
発酵食品に含まれる酵素や乳酸菌などの有効成分には代謝を高める効果があります。
また、腸内にある善玉菌が理想的なバランスとなることで腸内環境が整い、酵素の働きがスムーズになります。これにより、基礎代謝が上がりやすくなり、ダイエットに役立ちます。
加えて、善玉菌が増えることで食欲がコントロールしやすくなるので食べ過ぎや間食を予防し、自然とカロリー制限しやすい体質に近づけてくれます。また便秘解消によりお腹のハリが抑えられる効果も期待できます。
美肌・美髪効果
腸内にある増えすぎた悪玉菌が作る有害物質は、ニキビや吹き出物などお肌のトラブルの原因にもなります。
発酵食品を食べることで得られる善玉菌によってお腹の調子が整うと、お肌や身体そのものに悪影響を与える有害物質や老廃物などがお通じとして排出されます。
こうしたお肌のトラブルの原因を減らすことは、肌荒れの改善につながるのです。
また、チーズや納豆、お味噌などのタンパク質を豊富に含む発酵食品には、美しい髪の元となり、それら3つに共通して豊富に含まれるビタミンB2は、ターンオーバーを促進する効果があるので、健康的でイキイキとした美しい肌や髪を作ってくれます。
便秘解消効果
発酵食品を摂ることで善玉菌が増え、腸内細菌を理想のバランスに整えると、腸の運動(腸蠕動)が活発になり便秘や下痢などのお腹の不調を整えることにつながるといわれています。
免疫力向上効果
腸内には多くの免疫細胞が集まっています。
私たちの体には、外から⼊ってきた病原菌などを排除するシステムが備わっています。通常、感染源となるウイルスや病原菌などは⼝や⿐から体内へ侵⼊するため、腸までの消化管は常に感染源曝露の脅威にさらされています。
この外敵から体を守るために、腸には免疫細胞の約70%が集まっており、「腸管免疫」と呼ばれています。
腸管免疫は腸内フローラと重要な関わりを持っていることが最近の研究でわかっています。そのため、腸内フローラを整えることは免疫細胞の活性化につながると考えられています。善玉菌が増えて働きが活発になることで、免疫力向上やアレルギー症状の緩和につながるとされています。
発酵食品の一覧と1日の摂取量

摂りすぎなければ健康に良い効果をもたらしてくれる発酵食品。
今回は代表的な発酵食品の1日の目安摂取量をお伝えします。
ヨーグルト
農林水産省が発表している「食事バランスガイド」によれば、成人女性のヨーグルトの1日の目標摂取量は100~200gとなっています。
これは一般的なカップで売られているヨーグルトの1~2つ分に該当します。
味噌
厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準」によれば、食塩は1日6g未満の摂取にとどめることが推奨されています。
味噌に置き換えるとその量はおよそ大粒の真珠くらいの大きさで、重さは6g程度です。大さじ3分の1程度がお茶碗1杯分の味噌汁を作るときに使用して良い量となっています。
納豆
農林水産省が出している「食事バランスガイド」によれば、他にタンパク質(お肉・お魚・豆腐など)をとっている場合、成人女性であれば納豆は1日1パック(50g)程度の摂取に留めることが推奨されています。
ですが、他に何もタンパク質を取らない場合、納豆は1日3〜5パック食べて良いとされています。
しかし、納豆のみを摂りすぎて他にタンパク質源を何も食べないよりも、バランスよくお肉やお魚を食べる方が健康的に良いとされています。よって納豆は1パック程度にとどめ、お肉やお魚を食べるようにしてください。
また、心臓の薬であるワーファリンを飲んでいる方は納豆を食べてはいけません。ワーファリンは「抗凝固剤」といわれる薬で、血をサラサラにして血栓をつくりにくくする効果があり、心筋梗塞などの治療や予防に使われます。
納豆を食べると腸内でビタミンKが合成されるため、ワーファリンの効果を弱めてしまうのです。これは心筋梗塞の再発に繋がってしまいます。
ワーファリンを服用している人は、絶対に納豆を食べてはいけません。
キムチ
キムチの1日の摂取量の上限は50gと言われています。
食塩は1日6g未満の摂取に抑えることが目標であり、塩分の多いキムチに換算するとおよそ小皿に1杯分程度となります。美味しいのでたくさん食べたい気持ちもありますが、塩分過多になってしまわないためにも少量に抑えることが必要です。
チーズ
一般的な30~50代の女性の平均代謝量から選定される、1日のチーズの上限摂取量はプロセスチーズ(6Pチーズ)でいうと1つ程度(20g)です。
なお、チーズには多種多様な種類があり、種類によってカロリーも様々です。ダイエットを目的とするのであればカロリーが少ないカッテージチーズを少し多めに、タンパク質を摂取して美肌・美髪・免疫力をあげたいのであればパルメザンチーズを小さじ1杯程度サラダにパラパラとかけて少なめにとる、など目的に合わせて量を変化させていきましょう。
ぬか漬け
前述した通り、厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準」によれば、食塩は1日6g未満の摂取にとどめることが推奨されています。
日本食品標準成分表2020年版によると、ぬか漬けはきゅうりであれば100gあたり5.3g、大根であれば3.8gの塩分が含まれています。
もちろん、1日のお食事でぬか漬け以外からも塩分は摂取することになりますので、きゅうりであれば1日3切れ程度、大根であれば4切れ程度、どちらも小皿1盛り分が摂取量の目安となります。
塩分過多に気をつけるのであれば、間違ってもぬか漬けのきゅうり1本丸々食べてしまうのは摂りすぎと考えられます。
※参考:
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
エーザイ株式会社「ワーファリン」
私の実際の発酵食品生活【1日の献立例】

発酵食品を食生活に取り入れたり、意識的に健康的な生活を送っている30代OLの1日の食生活をまとめてみました。是非参考にしてみてください。
朝:
起きたら歯磨き後に白湯または常温の水をコップ1杯飲む!これで胃腸を動かして効果的に発酵食品を摂るようにするよ。
朝ごはんはオートミールにヨーグルトをかけたものを。オートミールの食物繊維とヨーグルトの乳酸菌がお腹を活性化させます。
ヨーグルトは少しで良いから摂りすぎにも効果的。朝起きて最初に飲んだお白湯のおかげでオートミールが膨らんでお腹いっぱいに◎
ヨーグルトは無糖のものを選んで、ちゃっかりダイエットにも効果あり!
昼:
ランチは会社の同僚と外食。
パスタ屋さんでは納豆パスタを選択!
納豆に含まれる納豆菌は熱にも強いから、炒められてもちゃんとお腹に届いてくれます。
外食でもちゃっかり発酵食品摂れちゃった。
夜:
昼は外食しちゃったから、夜は自炊だ!
今日は手軽にできる豚キムチにしようかな。キムチは小皿1杯分にして、塩分控えめに!
でも辛いのは好きだから唐辛子をちょっとだけ足してスパイシーにしちゃおう。お味噌汁と冷奴も合わせて、発酵食品満載の豚キムチ定食が完成。
お風呂上がりの水分補給。ただのお水じゃなくて、最近はやりの果実酢をちょこっと足してみる。
実は寝る2時間前に発酵食品を摂ると良いって言われてるらしい。
今日は朝にヨーグルトを食べたけど、食べてない日は飲むヨーグルトをお風呂上がりに飲むのもいいかも。
発酵食品のおすすめレシピ

今回は、平日のお仕事がある日でも取り入れやすい、簡単にできるおすすめ発酵食品レシピを紹介します。是非試してみてくださいね。
時間がない朝にも!オートミールヨーグルト

調理時間の目安:約3分
材料(1人分)
- オートミール
- 30g(大さじ5杯)
- 水
- 100ml
- ヨーグルト
- 50g(一般的なカップヨーグルトの半分)
作り方
- オートミールに水を加えて、電子レンジで1分半~2分温めます。
- ヨーグルトを加えて出来上がり。
お好みでドライフルーツやバナナなどを添えても美味しいです。
簡単10分で!定番豚キムチ

調理時間の目安:約10分
材料(1人分)
- 豚肉
- 100~150g
- キムチ
- 50g(小皿1杯分)
- ☆唐辛子
- 適量(辛いのが苦手な方はお出汁大さじ3杯 もしくは細切りにした昆布)
作り方
- 中火で豚肉を炒め、火が通ったらキムチを加えます。
- お肉とキムチを馴染ませたら火を止め、☆を加えて出来上がり。
キムチに味がついているため、何も味付けをしなくて良いのが良いところ。お出汁や昆布を加えると味に深みが出ます。
辛いものが得意な方は、キムチを増やすのではなく、唐辛子を加えて塩分を調節してください。
お家で簡単。アボカド納豆パスタ

調理時間の目安:約15~20分
材料(1人分)
- パスタ
- 100g
- アボカド
- 1個
- 納豆
- 1パック
- かいわれ大根
- お好みの量
- ☆白出汁
- 大さじ1
- ☆醤油
- 小さじ2
- ☆牛乳
- 大さじ2
- ☆マヨネーズ
- 大さじ2
- ☆コショウ
- お好みの量
作り方
- パスタを表示されている時間茹でます。
- アボカドをサイコロ状に切ります。
- ボールの中で☆・納豆・納豆のタレを混ぜ合わせ、アボカドを半分加えておきます。
- しっかりと湯切りしたパスタを3と混ぜ合わせ、お皿に盛ります。
- 残ったアボカドと貝割れ大根を盛り付けたら完成です。
お好みでパルメザンチーズを振り掛けても美味しいです。
発酵食品を上手に生活に取り入れて◎

体にいい発酵食品。
ぜひ摂りすぎに気をつけて日々のお食事に取り入れ、健康な体を手に入れてくださいね。