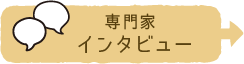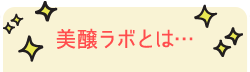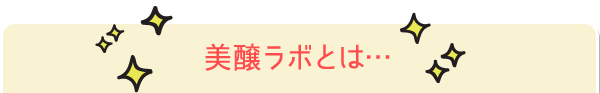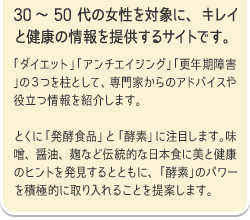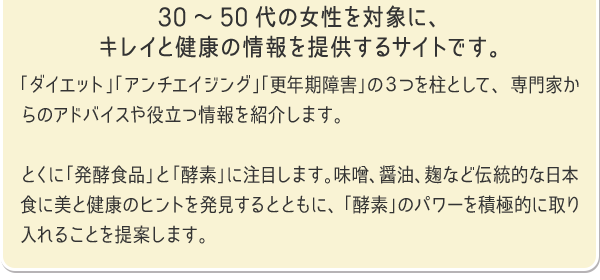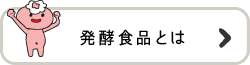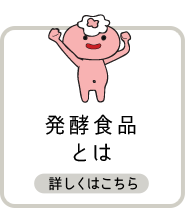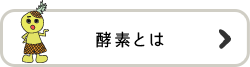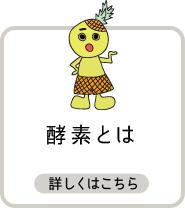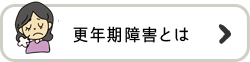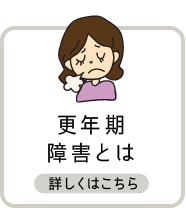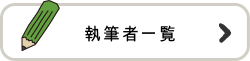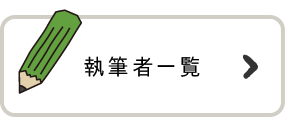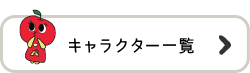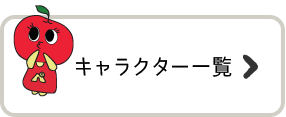発酵食品であるキムチは、ダイエットや美容効果に役立つとされています。
そんなキムチのメニューや腸活レシピや1日の摂取目安量、食べ続けた結果得られるメリットについて詳しく解説しますね。
年齢を重ねると基礎代謝が落ちたり、ホルモンバランスが崩れたりと私たちのからだも変化していて、思うようなダイエットの結果が出なかったり、辛くて続かなかったりという人もいるのではないでしょうか。
また、便秘で腸の不調を感じている人にも、腸の調子を整えて健康的で美しくダイエットができるキムチの役立つ栄養情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
発酵食品の基礎知識|キムチの乳酸菌が体に良いメリット

キムチは、発酵させた野菜に唐辛子やにんにく、ショウガなどの薬味を加えて作られる韓国の伝統的な食品です。乳酸菌とは発酵により糖から乳酸をつくる微生物のことで、腸内で悪玉菌の繁殖を抑え、腸内環境を整える大切なはたらきがあります。
人にとって有益な菌なので「善玉菌」とも呼ばれていますね。
有名なヨーグルト・チーズだけでなく、キムチやぬか漬けなどの漬け物・日本酒とさまざまな発酵食品の製造過程で使われています。
乳酸菌は腸内で大腸菌などの悪玉菌の繁殖を抑え、腸内菌のバランスを整えるはたらきがあるため、便秘の人にも朗報ですね。
また、コレステロールの低下や免疫力をあげたい人もサポートしてくれる、強い味方の食品です。
ほかにも、キムチには野菜から摂れるビタミン・ミネラル・食物繊維などの栄養素が豊富に含まれているのもうれしいですね。
腸の調子を整え免疫力をアップ!自律神経との関係も
キムチには植物性の乳酸菌が多く含まれ、「動物性」由来乳酸菌と「植物性」由来の乳酸菌の2種類があります。
動物性乳酸菌と植物性乳酸菌
| 動物性乳酸菌 | 乳酸菌 | ヨーグルト・チーズなど |
|---|---|---|
| 肉・魚 | ドライソーセージ 生ハム くさやなど | |
| 植物性乳酸菌 | 野菜・豆 | キムチ・ぬか漬け 納豆など |
| 調味料 | 味噌・醤油・コチュジャン 酢など | |
| 酒 | 日本酒・ワイン・ビールなど | |
| お茶 | 烏龍茶・紅茶・碁石茶 | |
| デザート | くずもち・ナタデココなど |
動物性乳酸菌は、主に乳の糖をエサとして生育し約20種類あります。一方で植物性乳酸菌は、野菜や大豆・米などのブドウ糖・果糖・ショ糖・麦芽糖などのさまざまな糖をエサとして利用することができ、動物性乳酸菌より10倍以上の種類があるといわれています。
塩分も含まれ微生物に良い条件ではない環境の中で育つ植物性乳酸菌は、動物性乳酸菌より強い生命力を持ち、体内で胃酸や消化液をくぐりぬけ、生きて腸まで届く確率が高いと考えられています。
腸の調子が整うとお通じもよくなり、自然と体重が減りますね。
また、腸と自律神経には深い関係があり、ホルモンを通してお互いが情報交換をしています。
免疫システムに関わる免疫細胞の7割は腸に生息しているといわれ、腸内でウィルスなどの病原菌と戦っています。
免疫細胞は血液にのり体の隅々までめぐり、至る所で体を守り戦っているため、腸の健康の影響は大きいといえるでしょう。
免疫力を高めるには、腸が健康であることが大切ですね。
そして、自律神経が整うと血行も良くなるため、血行が良くなると、少し動くだけでも身体がぽかぽかして、脂肪が燃焼しやすい身体になります。
また体温は1度上がると免疫力は30%アップするともいわれています。
すべて繋がっているのですね!
キムチに含まれる成分は、ダイエットにも適しています。
キムチでダイエット|美しく痩せて健康美を目指す

キムチは、野菜の発酵食品で低カロリーであること、食物繊維も豊富なので、満腹感を与えて食べ過ぎを抑える効果もあり、ダイエットにもおすすめの食品です
白菜キムチ (可食部100gあたり)
| エネルギー | 27kcal | ビタミンA | 170㎍ |
| タンパク質 | 2.3g | ビタミンK | 42㎍ |
| 脂質 | 0.1g | ビタミンB1 | 0.04㎎ |
| 炭水化物 | 5.4g | ビタミンB2 | 0.06㎎ |
| カリウム | 290㎎ | 葉酸 | 22㎍ |
| カルシウム | 50㎎ | ビタミンC | 15㎎ |
| リン | 48㎎ | 食物繊維総量 | 2.2g |
※ビタミンA(β-カロテン当量)
参考資料:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より抜粋
- 皮膚や粘膜などの健康維持にビタミンA 脂溶性のビタミンの一種で、主に視力の維持や免疫機能のサポート、皮膚や粘膜の健康維持に役立ちます。
- 糖質の代謝を助けるビタミンB1 エネルギー代謝に関わるビタミンB1は糖質の代謝を助け、疲労回復効果があります。 また、脳と神経を正常に保つはたらきもあります。 水に溶けやすいので、スープや汁物にすると効率的に摂取できます。
- 脂質の代謝をサポートする!ビタミンB2 ビタミンB2は脂質をエネルギーに変えるために欠かせない大切なビタミンです。 脂質は新しい細胞を作る手助けをするので、皮膚や粘膜などを健康に保つサポートをします。 子どもや胎児の発育を助けるはたらきもあるため「成長ビタミン」ともいわれています。
- 美肌づくりにビタミンC ビタミンCはコラーゲンの合成に関わるビタミンで、活性酸素を除去する抗酸化作用がありストレスから体を守るはたらきをします。 また、皮膚のシミやしわを防いだり、傷や炎症の治りを助けたり、粘膜を強くして健康に保つはたらきもあります。 水溶性ビタミンは熱に弱い性質があるので、生で食べると良いですね。
- 体ぽかぽかカプサイシン 辛味成分のカプサイシンは代謝を促進し、脂肪燃焼を助けることが期待されます。
- 強い抗菌力のアリシン にんにくをすりつぶしたときに生じるアニリンは、強い抗菌作用があります。
キムチを毎日食べ続けるとどうなる?いつがベスト?
キムチの整腸効果を活かすには、夕食に食べるのがおすすめです。
腸の動きが活発な日中は、キムチの栄養成分の消化管の中にとどまる時間が短いからです。
腸の動きが緩くなる夕食に摂ることで、乳酸菌の滞在時間が長くなるため善玉菌が増える可能性が高くなります。
臭いが気になる人にも夜の摂取の方が良いですね。
乳酸菌は加熱すると弱いので、生のまま食べた方がより腸に高い効果が得られると期待されています。
ただし、弱った植物性乳酸菌もしっかり善玉菌のエサとなるので、実はきちんと役に立っているので心配はいりませんよ。
キムチを食べるときの注意点
発酵食品のキムチが健康に良いからといって過度に摂取してしまうのは危険です。
一部のキムチには多くの塩分が含まれている場合があり、塩分の摂取過多は高血圧や水分バランスの乱れにつながる可能性があるため、過剰な摂取には注意が必要です。
また、キムチに含まれる成分に対してアレルギー反応を起こすこともあります。
とくに、シーフードや魚醤を使用したキムチは、アレルギーを引き起こす可能性があるので、アレルギー状況に合わせてよく確認してくださいね。
キムチに含まれるカプサイシンは、胃腸の弱い人や消化不良の症状がある人は、摂取量を調整する必要があります。
また購入するときのポイントは、発酵しているキムチを選ぶことです。
発酵しているキムチとは、塩漬けした白菜などに薬味を加え低温で発酵させたものです。
発酵してないキムチはキムチ味の調味料で野菜を浅漬けにしたものです。
発酵キムチは乳酸発酵しているので、乳酸菌が数多く含まれますが、発酵していないキムチは、キムチ風浅漬けしただけなので乳酸菌は入っていません。
野菜が持つ食物繊維やビタミンなどはとることができるので体に良くないということではありませんが、購入するときは自身でよく確認してくださいね。
キムチくんマークがついているキムチを購入するのもいいですね。
このマークは、韓国産の熟成発酵キムチに掲載が許可されたマークのことです。
ダイエットの落とし穴|きつい食事制限は危険
年齢を重ねると代謝も落ちるため、ダイエットしても痩せないという焦りが出てくるかもしれません。
ダイエットとして糖質制限や野菜サラダをメインにした食生活にしてしまいがちではないでしょうか。
糖質制限や野菜サラダをメインにした食生活に偏ることは注意が必要です。
極端な食事制限は、栄養失調を起こしたり骨粗鬆症になりやすくなったりと反対に健康に悪影響を及ぼす可能性があるので、食事制限を極端にすることは避けてくださいね。
制限するのであれば、お酒などのアルコール類やジュース、ジャンクフードなどの間食から摂取を減らし、食事は糖質も適切な量を摂るようにバランスの取れた食事を心掛けましょう。
肉や魚、卵、豆腐、乳製品などのタンパク質の摂取も重要で、筋肉の分解を抑える働きがあり、筋力の低下を防ぐ役割があります。
そこに、植物性乳酸菌であるキムチをプラスすることで効率よくダイエットできますよ。
オススメ記事
【管理栄養士が解説】発酵食品の健康・美容効果とは?おすすめレシピもご紹介!
発酵食品の効果とは?管理栄養士の筆者が、美容・健康への効果を解説します。日々の食事に取り入れることで、免疫力アップやアンチエイジングを目指せますよ。おすすめの発酵食品と食べ方、ちょっとした工夫が美味しい秘密のレシピもご紹介します。

キムチの摂取量目安と継続するポイント

キムチは1日に約50g程度を目安として摂取することが推奨されています。
ただし、キムチの辛さや塩分濃度によっては摂取量を調整する必要が出てくることもあります。
臭いが気になる人は、軽減する方法としてキムチを冷蔵庫に保存することや、食べる直前に袋や容器を開けるなどの対策などがあります。
また、発酵食品は1回だけの摂取ではなかなか変化を感じられません。
まずは2週間程度、意識して食べてみましょう。
納豆などの発酵食品同士で食べ合わせたり、善玉菌のエサとなる食物繊維と一緒に摂取するのも腸活におすすめです。
食物繊維は血糖値の上昇を抑えてくれるはたらきもありますよ。
キムチを活用して家でも作れると良いですね。
家で作れるキムチと簡単腸活レシピ
ここで、簡単に作れるキムチの作り方を紹介しますね。
基本的なキムチの作り方

調理時間の目安:約~分
材料(~人分)
- 白菜の漬けキムチ用
- 1個(約1.5kg)
- 塩
- 1/4カップ
- 砂糖
- 小さじ2
- 唐辛子粉
- 小さじ
- にんにく(すりつぶす)
- 4片
- 生姜(みじん切り)
- 小さじ1
作り方
- 白菜をきれいに洗い、水気を切ります。
- 葉を1枚ずつはぎ取り、適当な大きさに切ります。
- 切った白菜に塩をまぶし、全体に均等に塩を広げます。
- 1時間ほど放置し、白菜がしんなりするまでおきます。
- しんなりした白菜を水で洗い、水気をしっかり切ります。
- ボウルに砂糖、唐辛子粉、にんにく、生姜、塩漬け海苔(あれば)を入れ、よく混ぜ合わせます。
- 白菜を手で押さえながら、作った調味料をしっかりと白菜に絡ませます。手袋を使用すると唐辛子の刺激から手を守ることができます。
- 漬けたキムチを室温で1〜2日ほど発酵させ、酸味が増して美味しくなるまで待ちます。
発酵が進んだら、冷蔵庫で保存してくださいね。
このレシピは基本的なキムチの作り方ですが、個々の好みに合わせて調味料の量や具材を調整することもできます。
また、さまざまな野菜や具材を加えることでバリエーションを楽しめますよ。
またキムチを活用した腸活レシピの一例をご紹介しますね。
キムチサラダ

調理時間の目安:約~分
材料(4人分)(1人分約85kcal)
- キムチ
- 80g
- レタス
- 3枚(約90g)
- トマト
- 中1個(約200g)
- きゅうり
- 半分(約50g)
- ごま油
- 大さじ2
- いりごま
- 大さじ1
作り方
- キムチを細かく切ります。
- ボウルにレタス(ザク切り)きゅうり・トマト(乱切り)を加えます。
- キムチとごま油といりごまを加えてよく混ぜます。
【キムチスープ】

調理時間の目安:約~分
材料(4人分)(1人分約151kcal)
- キムチ
- 80g
- 豚肉 細切れ
- 200g
- 玉ねぎ
- 中1/2個(約200g)
- もやし
- 1袋(約200g)
- にんにく
- 小さじ1(みじん切り)
- 中華だし
- 大さじ1
- 酒
- 大さじ1
- 醤油
- 小さじ2
- 水
- 適量
- ごま油
- 大さじ1
作り方
- 鍋にごま油を熱し、みじん切りにしたにんにくを炒めます。
- 豚肉を加えて炒め、玉ねぎも加えて炒めます。
- キムチともやしを加え、軽く炒めます。
- 水を加えて煮込みます。
- 調味料を加えて味を整え、具材が柔らかくなったら完成です。
豆腐やしめじなどを入れても良いですね。
キムチチャーハン

調理時間の目安:約~分
材料(2人分)(1人分約350kcal)
- キムチ
- 80g
- 豚肉ひき肉
- 100g
- 玉ねぎ
- 1/2個(約50g)
- ごはん
- 300g
- にんにく
- 小さじ1(みじん切り)
- ごま油
- 大さじ1
- 醤油
- 小さじ
- 中華だし
- 大さじ1
- 塩こしょう
- 少々
作り方
- フライパンにごま油を熱し、にんにくと豚肉ひき肉を炒めます。
- 玉ねぎを加えて炒め、キムチも加えてさらに炒めます。
- ご飯を加え、全体が均一に混ざるまで炒めます。
- 醤油、塩、胡椒で味を調え、完成です。
お好みで卵をトッピングするのもおすすめです。
ほかにもキムチを利用したさまざまな料理がありますので、料理にアクセントや風味を与えることができる万能な食材です。
美味しいキムチの腸活レシピを活用してお楽しみください。
発酵食品のキムチは腸の調子を整えダイエットや美容効果も抜群
発酵食品であるキムチはさまざまな体に良いメリットがありますね。
キムチの体にメリットとなる成分
| 腸の調子を整える | 乳酸菌・食物繊維 |
| 美肌づくりに | |
| 体の機能を正常に保つ | ビタミン・ミネラル |
| 脂肪燃焼や血行を良くする | カプサイシン |
| 抗菌作用 | アリシン |
1日50g程度の適量を夕食に最低2週間ほど続けてみることがポイントなので、試してみてくださいね。
参考資料:
山梨県生連 eヘルスネット 乳酸菌 eヘルスネット カプサイシン 厚生労働省 ビタミンA 厚生労働省 水溶性ビタミン 厚生労働省 キムチ 日本食品標準成分表2020年版(八訂) 和 食育 東京農業大学 植物性乳酸菌 わかさの秘密 乳酸菌 大塚製薬 自律神経を高めるには「自律神経」と「腸内環境」と整えよう
オススメ記事
発酵食品の手作りに子どもと挑戦してみた◎味噌やキムチの簡単レシピをご紹介
発酵食品の手作りに栄養管理士の筆者が挑戦してみました。初めて作る味噌に子どもたちは大感激。他にも、水キムチ、甘酒などの発酵食品の手作りレシピをご紹介します。初心者でも失敗しない簡単な方法がありますよ。