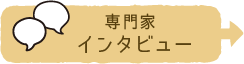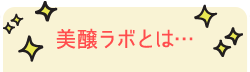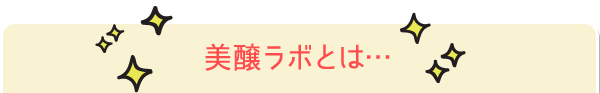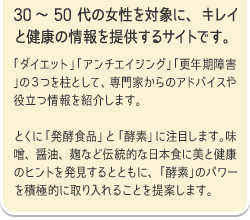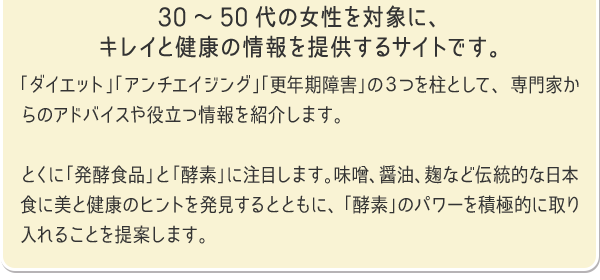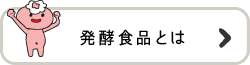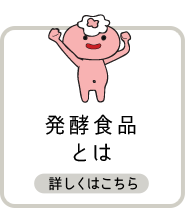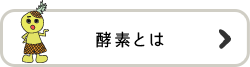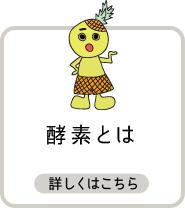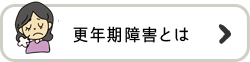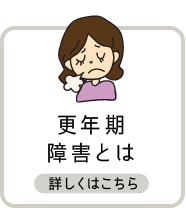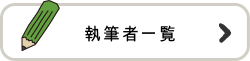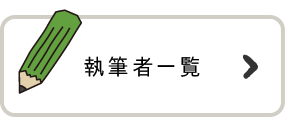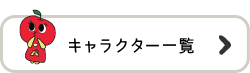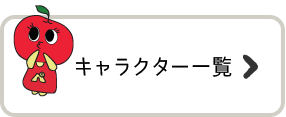中華料理に欠かせない豆板醤。
エビチリや麻婆豆腐など最近は、本格的な調味料を使って自作する方も増えています。
中華調味料で「醬」とは味噌のような発酵食品を指します。
もしかしたら、豆板醤は辛味をつける調味料くらいの認識かもしれません。
原材料や使い方など、まだ知らないこともあるでしょう。
そこで、今回は豆板醤について解説します。
また、豆板醤を使った簡単薬膳スープのレシピもご紹介しますので参考にしてください。
目次
豆板醤ってどんな調味料?

豆板醤は、絡みを出すときに使う中国の調味料です。
単に唐辛子を使う時と比べると、辛味の中に旨味が出て料理が美味しく仕上がります。
もしかしたら、豆板醤は辛味を出すだけの調味料という使い方をしているかもしれませんね。
そこで、豆板醤について詳しく説明しようと思います。
また、最近よく見かけるようになったコチュジャンとの違いについても解説しておきましょう。
豆板醤とは
元々、「醬」とは材料を発酵・熟成させた調味料のこと。
日本の味噌の類になりますが、もっと熟成を進めた調味料になります。
その中でも豆板醤は、辛味を出すときに活用される調味料。
豆板醤の作り方は、そら豆に大豆や麹と唐辛子の塩漬けなどを加えて発酵させます。
そして、豆板醤は加熱することで香りと旨味が増します。
そのため火を通す使い方が多くなります。
豆板醤とコチュジャンの違い
豆板醤と似た調味料にコチュジャンがあります。
味やテクスチャーが似ているので混同されている方もいるかもしれません。
しかし、これらは似て非なるもの。
コチュジャンは韓国発祥の辛味と甘味のある調味料になります。
原材料は、米や餅米を麹で糖化させ唐辛子を加えた発酵調味料になります。
糖分が多いので火を通すと、豆板醤に比べて焦げ付きやすいという違いがあります。
そのため、豆板醤は火を通す調理向きと言えるでしょう。
また、コチュジャンは生食もできるので、そのまま生野菜などと食べる方が相性が良いかもしれません。
豆板醤の保存方法

豆板醤は、購入して1回で使い切るということは、ほとんど無いと思います。
では、豆板醤の保存はどうしたら良いか。
豆板醤は、辛味が強く塩分も多い食材です。
そのため、腐敗は進みにくいと言えます。
しかし、発酵食品ですのでカビに弱いという特徴があるので注意してください。
そこで、カビの繁殖を抑えるためにおすすめの保存方法は「冷蔵保存」。
開封後は、密閉容器で冷蔵庫で保存するようにしましょう。
半年くらいは、保存可能になります。
豆板醤を使ったピリ辛薬膳スープ

豆板醤の特徴について分かってきたと思います。
それでは、豆板醤の特徴を活かしつつ、美味しく簡単に出来る薬膳スープレシピをご紹介します。
えびときのこ美肌トマトスープ
薬膳ではトマトやえびは、肌に良いと言われています。
豆板醤とニンニクで代謝も活性化して美肌に繋げましょう。
材料
- ニンニク
- 1片
- 豆板醤
- 小さじ1/2
- トマト
- 3個
- えび
- 8尾
- しめじ
- 1/2房
- 鶏がらスープの素
- 大さじ1
- ごま油(オリーブオイル)
- 20cc
作り方
- トマトを湯むきして皮を剥く
- トマトをミキサーにかけ、ざるなどで種を濾す
- ニンニクを微塵切りにする
- 鍋に油とニンニクと豆板醤を入れ弱火で炒める
- 香りが出てきたらエビとキノコを入れ少し焦げ目をつける
- 濾したトマトを入れ鶏ガラスープの素を入れる
- 沸騰させないように加熱し、湯気が立ってきたら火を止める
- 器に盛り付け、ごま油かオリーブオイルを垂らし完成。
ピリ辛卵気力回復スープ
豚肉の疲労回復作用と卵の気力補強ができます。
元気を取り戻したいときに豆板醤の辛味が刺激になり効果を高めてくれます。
材料
- 豚肩ロース
- 1枚
- 溶き卵
- 1個
- カブ
- 1個
- ニンニク
- 1片
- 生姜
- 5g
- 豆板醤
- 小さじ1/2
- 甜麺醤
- 大さじ1〜2
- 鶏ガラスープ
- 500cc
- ごま油
作り方
- ニンニクと生姜を微塵切りにする
- 豚肩ロースを一口大にカットする
- カブを8カットし、皮を剥く
- ニンニク・生姜・豆板醤を弱火で炒める
- 香りが出てきたら豚方ロースを入れ焼き目をつける
- 鶏がらスープを少し入れ甜麺醤を溶かす
- 残りの鶏がらスープと食材を入れ一煮立ちさせる
- 溶き卵を流し入れる
- 器に盛り付けてごま油を垂らし完成
薬膳ダイエットスープ
カロリーを抑えつつ栄養と代謝をあげる薬膳スープ。
薬膳では、酸味は引き締め作用がある味になります。
レモンの酸味も助けとなってダイエット効果が期待できそうです。
材料
- 鶏モモ肉
- 1枚
- アサリ
- 8個
- もやし
- 30g
- 春雨
- 30g
- 酒
- 50cc
- 豆板醤
- 小さじ2
- 鶏がらスープ
- 500cc
- ナンプラー
- 大さじ1
- レモン汁
- 大さじ1
- フライドガーリック
- 5g
作り方
- 鶏肉を一口大にきり、アサリを洗う
- フライパンで鶏肉を焼き焦げ目を少しつける
- 豆板醤を入れ油に馴染ませる
- 酒とアサリを加えてアルコールを飛ばす
- 鶏がらスープを入れ一煮立ちさせる
- 灰汁が出ていたら取る
- 春雨を入れ柔らかくなるまで茹でる
- もやしを入れ一混ぜする
- ナンプラー、レモン汁を入れる
- 器に盛り付けフライドガーリックをトッピングして完成
オススメ記事
塩麹の基本の作り方|保存期間・完成の見極めポイント・使う道具まで
塩麹をおうちで美味しく手作りしませんか?発酵食品を日常に簡単に取り入れるなら、塩麹から始めるのがおすすめです。いつもの調味料の代わりに、料理の一工夫に、と様々な方法で使うことで、食卓が健康的になりますよ。初心者でもお気軽にできるレシピをご紹介します。

これで豆板醤は強い味方

今回は、豆板醤について説明しました。
豆板醤は、そら豆に麹や唐辛子を加え熟成させた発酵調味料でした。
加熱することで香りと旨みが増すという特徴があります。
長期保存ができますので、日頃の料理に活用しやすいでしょう。
辛味を上手に使えるようになると、食欲を増すことができます。
また、発汗や代謝を促進してくれる作用も期待できるでしょう。
健康増進やダイエットにつながる料理も作りやすくなるかもしれませんね。