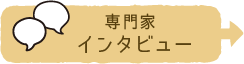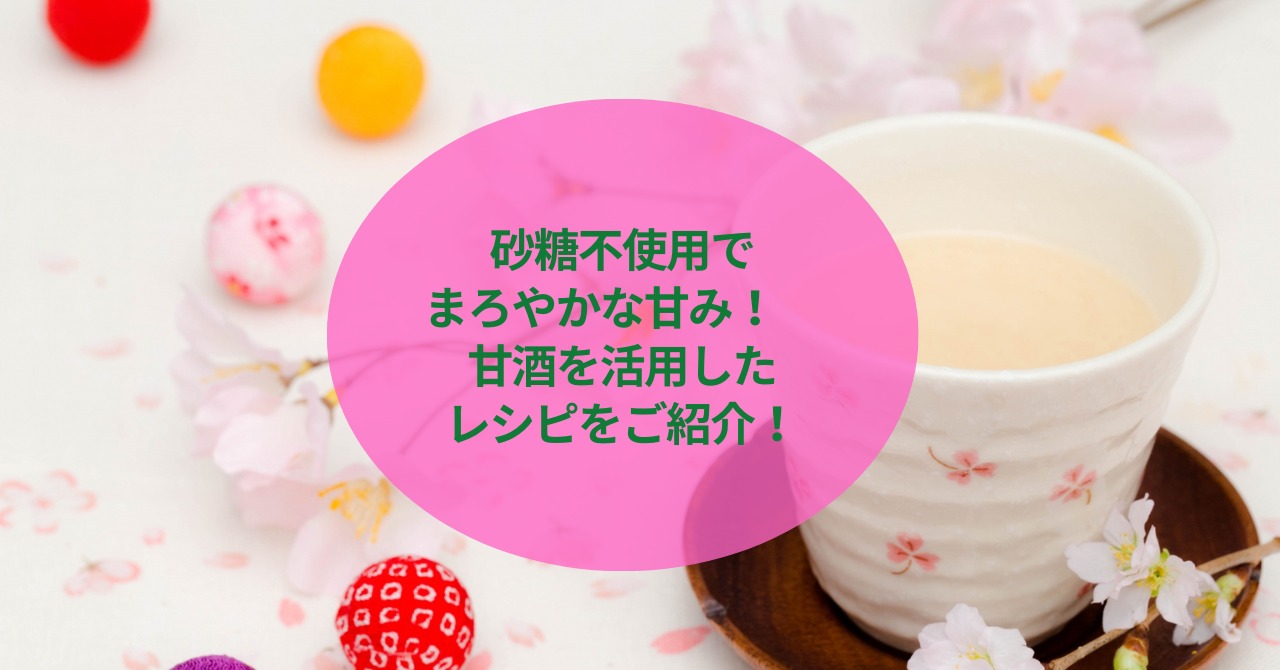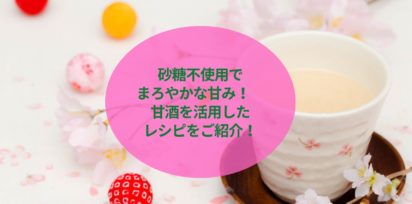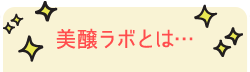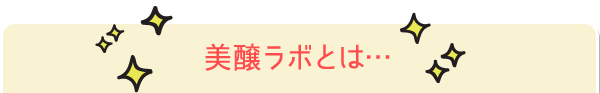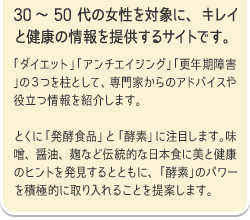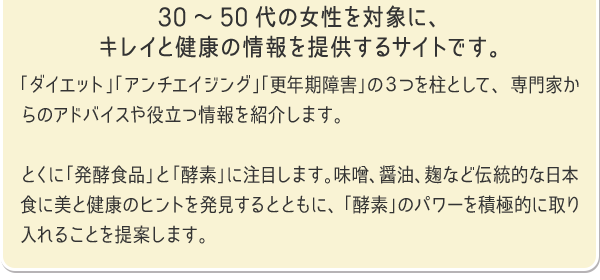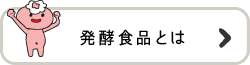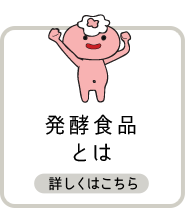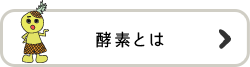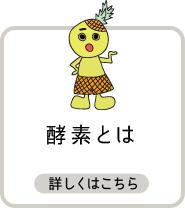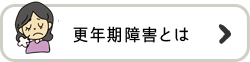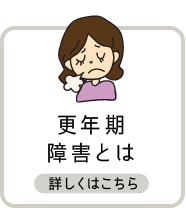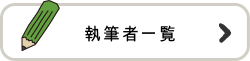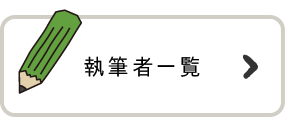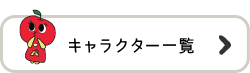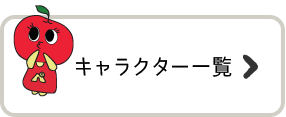甘酒はお料理に使用する砂糖やみりんの代わりとして使用することができます。
甘酒には米麹甘酒と酒粕甘酒の2種類がありますが、今回は米麹甘酒をお料理に活用していく方法をこの記事で紹介していきます。
甘酒アレンジ!おかず作りに活用するために知っておきたいポイント

甘酒がおかず作りにぴったりな理由と、活用する際のポイントをご紹介します。
ぜひこれを踏まえて、甘酒を様々なおかず作りに取り入れてみてください!
砂糖やみりんの代替として活用する
甘味の強さは使用する甘酒により異なりますが、上白糖やみりんなどの甘味調味料の代替として活用することが出来ます。
おかず作りに活用する際には味見をしながら好みの甘さに調整してみてくださいね。
肉や魚を柔らかく仕上げる
甘酒にはプロテアーゼというタンパク質分解酵素が含まれており、肉や魚の味付けに使うことで食材を柔らかく仕上げることができます。
味噌や醤油などの発酵調味料との相性も良く、甘酒の風味を活かした味付けが可能です。
消化を助け、腸内環境を整える
米麹甘酒の材料である米麹は100種類を超える酵素を作り出します。
その中でも有名な消化酵素はデンプンを分解するアミラーゼとタンパク質を分解するプロテアーゼです。
調味料に甘酒を使用することで胃腸の滞留時間を短くし、負担を軽減することができます。
甘酒に含まれる善玉菌は腸内環境を整えて、腸の消化能力を高める効果もあります。
甘酒を使ったメインのおかず

甘酒にはメインのおかずでよく使われるような、肉や魚のタンパク質を柔らかくするプロテアーゼという酵素が含まれています。
また、調味料として甘酒を使うことで柔らかく上品な口当たりにすることが出来ますよ。
醤油や味噌といった他の発酵調味料との相性も抜群です。
甘酒をおかず作りに使用する際に米粒感が気になる方は、ブレンダーやすりこぎでペースト状にしてください。
鰆(さわら)の甘酒味噌漬け焼き
鰆といえば西京焼きが有名ですが、甘酒を活用してアレンジしてみました。
焦げすぎが気になる方は、焼く前に調味料を十分に落とすことで防げますよ。

材料(2人分)
- 鰆
- 2切れ
- ☆甘酒
- 大さじ2
- ☆白味噌
- 大さじ
- ☆料理酒
- 小さじ2
作り方
- ジップロックなどの袋に☆と鰆を入れ、手で揉んでなじませる。
- 冷蔵庫で一晩寝かせる。
- 鰆から☆を指で落としてからフライパンで焼いたら完成です。
鯖の甘酒味噌煮
大人から子供まで大好きな鯖の味噌煮を甘酒でアレンジします。
甘酒の自然な甘味で上品な味わいに仕上がりますよ。

材料(2人分)
- 鯖(さば)2枚おろし
- 1枚
- ☆生姜
- 20g
- ☆水
- 200cc
- ☆料理酒
- 大さじ2
- ☆みりん
- 大さじ1
- ☆醤油
- 小さじ1
- ☆白味噌
- 大さじ1
- ☆甘酒
- 大さじ6(ご使用の甘酒によって調整してください)
作り方
- 鯖を半分に切ります。生姜は輪切りにします。
- 粒のある甘酒はブレンダーやすりこぎでペースト状にします。
※粒がそのままでも気にならない人はそのまま使用してもOKです。 - ☆を合わせてフライパンで煮立たせます。
- 鯖を加えて落し蓋をして10分程度煮たら完成です。
鶏肉と大根の甘酒醤油煮
甘酒を含む調味料で一晩漬け込むことで鶏もも肉がふっくら柔らかな食感になります。
三温糖でコクをプラスすることで味わいが深く仕上がります。

材料
- 鶏もも肉
- 250g
- 大根
- 1/3本
- Ⓐ甘酒
- 大さじ2
- Ⓐおろし生姜
- 5g
- 鶏ガラスープ
- 300ml
- Ⓑ醤油
- 大さじ3
- Ⓑ料理酒
- 大さじ3
- Ⓑ三温糖
- 大さじ1
作り方
- 鶏もも肉を一口大に切ります。
- ①にⒶをからませて一晩寝かせます。
- ②と一口大に切った大根をフライパンで焼き目が付く程度に焼きます。
- ③に鶏ガラスープを入れて煮立たせ、アクをとります。
- ④にⒷを加えて汁気が少なくなるまで煮込みます。
- 汁気が煮詰まり、大根と鶏肉に絡む程度になったら完成です。
豚肉の甘酒味噌焼き
オーソドックスな豚肉を焼いたおかずも、甘酒でアレンジを加えることで上品な味わいに変化します。
いつものおかずの味にバリエーションを付けたい時におすすめのアレンジです。
冷めても美味しく食べることができるため、お弁当の主役にもぴったりです。

材料(2人分)
- 豚ロース(しょうが焼き用)
- 200g
- ☆甘酒
- 大さじ1
- ☆味噌
- 大さじ1
- ☆おろし生姜
- 小さじ1
- ごま油
- 小さじ2
- キャベツ(千切り)
- 適量
作り方
- ☆を合わせてよく混ぜます。
- 豚ロースの両面に①を塗り、冷蔵庫で1時間以上置きます。
- フライパンにごま油を熱して、②を中火で焼きます。
- 皿に盛り付けて、お好みでキャベツを添えて完成です。
オススメ記事
酵素玄米・寝かせ玄米の圧力鍋を使った炊き方|健康食を手作り!
酵素玄米をご家庭の圧力鍋で炊く方法をご紹介します。玄米・小豆・塩を混ぜ合わせて炊飯し、時間をかけて熟成させた酵素玄米は、栄養たっぷりで健康効果が抜群。圧力鍋を使うと健康的な一品が簡単に作れますよ。よくある疑問にもお答えします。

甘酒を使った副菜

甘酒の優しい甘さがあるので冷めても美味しく食べることができます。
お弁当のおかずにもおすすめです。お弁当に入れる際には汁気に気をつけて入れてくださいね。
高野豆腐の照り焼き
今日のおかずにもう一品がほしい時に便利なおかずです。
高野豆腐は保存が効くのでいざというときの買い置きにもちょうどいい食材です。
タンパク質も豊富なので健康にも嬉しいアレンジレシピです。

材料
- 高野豆腐
- 4枚
- 大根おろし
- 適量
- 刻みねぎ
- 適量
- 片栗粉
- 適量
- サラダ油
- 大さじ2
- ☆醤油
- 大さじ2
- ☆みりん
- 大さじ1/2
- ☆甘酒
- 大さじ2
作り方
- 高野豆腐をお湯で戻します。ボウルの中で指や拳で押して何度か洗います。
(写真では高野豆腐をそのまま使用していますが、一口大に切ると食べやすいです。) - ①の水分を絞り、全体に片栗粉をまぶし、軽く手ではたきます。
- フライパンにサラダ油 大さじ1をひき、②を入れて焼きます。軽く焼き色がついたらひっくり返し、残りのサラダ油を入れて側面もまんべんなく焼きます。
- ☆を混ぜたものを入れ、③に絡める。
- お皿に盛り付けて、大根おろしと刻みねぎで飾り付けたら完成です。
きのこの甘辛煮
そのまま食べてもOK、うどんやそばのトッピングにも活躍するきのこの甘辛煮です。
食物繊維も豊富です。甘酒と組み合わせることで腸内環境を整える効果もアップする、身体にも嬉しいアレンジです。

材料
- お好みのきのこ
- 約300g
- サラダ油
- 大さじ1
- 料理酒
- 大さじ1
- 塩麹
- 小さじ1
- ☆醤油麹
- 大さじ2
- ☆甘酒
- 大さじ1
- ☆酢
- 大さじ1
作り方
- フライパンにサラダ油を熱して強火できのこを炒めます。
- 全体にサラダ油がまわったら、料理酒と塩麹を入れて蓋をして1分程度蒸し焼きにします。
- きのこから水分が出てきたら合わせておいた☆を入れ、好みの汁加減まで煮詰めます。
- 冷蔵庫で4〜5日程度日持ちもするので作り置きおかずやお弁当のおかずにもぴったりです。
甘酒を使った常備菜

甘酒を使用した常備菜をご紹介します。
こちらで紹介するレシピは甘酒を加熱せずに使うので甘酒の栄養をまるごと食べることができます。
ほうれん草と油揚げの胡麻和え
定番おかずのほうれん草の胡麻和えに甘酒をプラスすることで旨味とコクがアップします。
油揚げの代わりに人参やきのこ類でアレンジしても美味しく食べることができますよ。

材料(2人分)
- ほうれん草
- 1束
- 油揚げ
- 1枚
- 白すりごま
- 大さじ2
- ☆醤油
- 大さじ1
- ☆甘酒
- 大さじ2
作り方
- ほうれん草を茹でて冷水にとります。絞って根元を落とし3cm程度に切ります。
- 油揚げは細切りにしてフライパンで乾煎りし、焦げ目をつけます。
- 白すりごまに☆を加えます。
- ①〜③を和えて完成です。
ごぼうと人参のダブル麹漬け
食物繊維が豊富で健康のために積極的にとりたいごぼうを使用したおかずです。
甘酒と醤油麹で味付けをしますので、発酵食品を積極的にとりたい人にもぴったりなアレンジです。常備菜にもおすすめです。

材料(2人分)
- ごぼう
- 1本
- 人参
- 1/2本
- ☆醤油麹
- 大さじ2
- ☆甘酒
- 大さじ2
- ☆ごま油
- 大さじ1/2
- 白ごま
- 適量
作り方
- ごぼうの皮を包丁の背でこそぎ取り、ささがきにします。
※お好みで千切りや半月にしても食感が変わって楽しいです。 - 人参は皮をむき、ごぼうと同じ切り方に揃えます。
- ごぼうと人参を下茹でします。
- ジップロックに③とAを入れて空気を抜きます。
- 冷蔵庫で5時間程度寝かせたら完成です。
食べるときにごまをまぶすと美味しいですよ。
甘酒が余っても毎日のおかずにアレンジ◎

米麹甘酒は上白糖やみりんの代わりの甘味調味料として使うことができることをこの記事で紹介しました。
米麹甘酒を甘味調味料として使用することでビタミンB群、ミネラル類、アミノ酸、食物繊維などの栄養を普段のお料理にプラスすることができます。
余ってしまった甘酒を無駄なく活用したい人も、健康的な食生活に甘酒を積極的に取り入れたい人も、甘酒アレンジを楽しんでお料理に取り入れてみてくださいね。
オススメ記事
【発酵食品で免疫力をUPさせよう!!】腸内環境も整う食事法とは?
免疫力UPに効果的な発酵食品の秘密を解明。腸内免疫の要、発酵の力で健康的な生活を送れるよう、管理栄養士が発酵食品の免疫力について詳しく解説します。腸内環境を整えるための食事法から腸活のポイントまで。発酵菌が免疫細胞を活性化させる仕組みもご説明します。