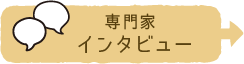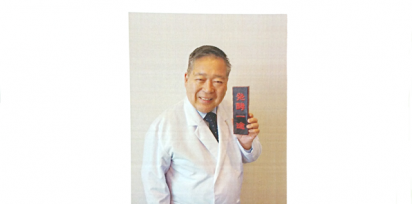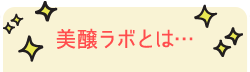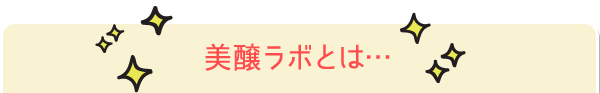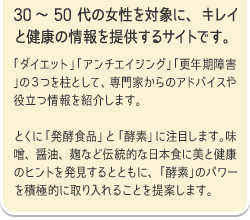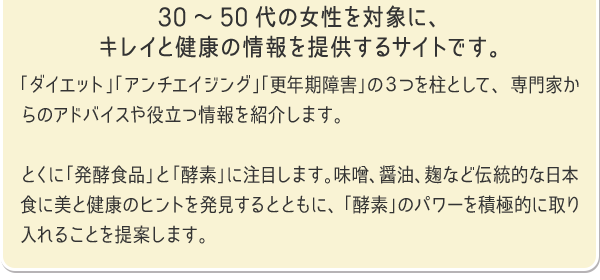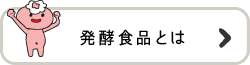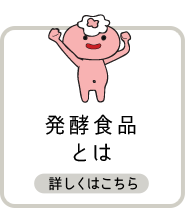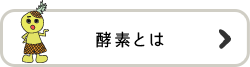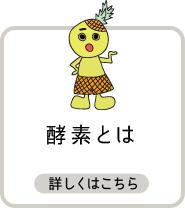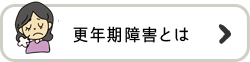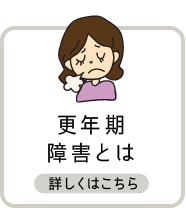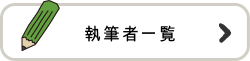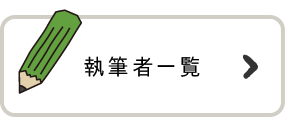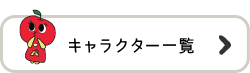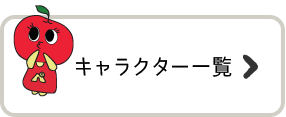玉川髙島屋で開催された、発酵学の権威である小泉博士のトークショー『発酵食品の4つの魅力』に行ってきました! 発酵学の奥深さと魅力にがっちり心を掴まれましたよ。
発酵のエキスパート小泉武夫博士

小泉武夫博士
そもそも、この小泉博士って何者? という方のために、簡単にご説明したいと思います。小泉博士は40年以上発酵学に携わっている、発酵のスペシャリスト。現在は、東京農業大学の名誉教授であり、日本経済新聞に「食あれば楽あり」というコラムも寄稿。最近では、発酵デリカテッセン カフェテリア「Kouji&ko(コウジアンドコー)」を運営するフードアンドパートナーズ の顧問を務めています。
NHKの「発酵は力なり」という番組に携わったことで「発酵仮面」というあだ名がついたこともあるとか。
講義開始! まずは、発酵食品を作る微生物達の紹介
発酵食品を作っている微生物達はこんなのです。

微生物
出していただいた甘酒を美味しく飲みながら耳を傾けていると、「甘酒などのアルコールは、酵母が糖を使って発酵し作られます。甘いと感じるのは、酵母が体内に保有できなくなった糖分、つまり、酵母の代謝物。人に置き換えればおしっこ! 」という言葉が。会場からはくすくす笑いが起こりましたが、なんというか、ええ、今飲んでる甘酒が甘いのは・・・・・・。なんとも言えない気持ちになりましたね、はい。
もちろん、私たちの体にもたくさんの微生物ちゃん達がいるわけで、その数はなんと40兆匹になるんだとか! 想像するとちょっと気持ちが悪いですね(笑)。
他にも、納豆菌は目に見えないほど小さくてもネバネバの糸をひいているとか。抗生物質も微生物が発酵によって作りだしたものだとか、知らない情報が満載。前談で私のハートはがっちりつかまれましたね。
トークショーのテーマは『発酵食品の4つの魅力』
さて、やっと本題のトークショー。今回のテーマは発酵食品の4つの特徴です。
<4つの特徴>
1:腐りにくい
2:究極の自然食品
3:独特の味と臭い
4:栄養成分が素晴らしい
では、詳しくみていきましょう。
【1】腐りにくい
発酵すると腐敗しにくくなるといいます。
例えば、牛乳を一晩常温で置いておいてみましょう。
・発酵させないと→翌朝には臭い始める
・牛乳+乳酸菌で発酵させると→プヨンプヨンに変わる。ヨーグルトが完成!

あくまで小泉博士の個人の好みですが、博士は賞味期限が切れたカリカリ納豆がお好き。納豆は発酵しているから腐らないというわけです。

そんな大好物を冷蔵庫の大掃除の際にみつけたときには、にぼしとあわせてすり鉢で粉末にし、納豆ふりかけを作るんだそうです。これが美味しいとか。
【2】究極の自然食品
発酵食品は、添加物で味付けしなくても美味しく食べられます。確かに、納豆だって醤油をかけるだけで食べられるし、本枯鰹節もそうですね。
最初、普通すぎてピンとこなかったのですが、旨み調味料をいっさい使っていないのに、十分旨みがあるのは確かにスゴイ。最近「無添加」表示のついた食品が増え、無添加だと良いとされる風潮にありますけど、そもそも納豆も本枯鰹節も完全に無添加商品ですね(笑)。
【3】独特の味と臭い
発酵食品には、独特の臭いがあるけれど、これが良いんだそうです。人は、この臭いがあるから、食べて問題ないものとあるものがわかるといいます。
それを裏付ける実験として、ある番組でどうしても食べないといけなくなったら、臭いだけで小学生はAとBどちらを選ぶかという実験を行ったことがあるようです。
A 腐ったサバ
(死んだネズミのような臭い)
B 世界一強烈な臭いを放つ発酵食品。ニシンの塩漬けシュールストレミング
(失神、または異臭騒ぎを引き起こす臭い。屋内開封厳禁と注意書きにある。)
その結果、94%の子供がBの発酵食品を選んだといいます。

これだけ聞くと、発酵食品は臭いものだと思ってしまいますが、日本酒の大吟醸なんかはフルーツを使ってなくてもとってもフルーティーないい香りがしますよね。これも発酵のおかげ。発酵していい臭いもうまれるんですね。
【4】栄養成分が素晴らしい
発酵食品は食品の栄養素を高めてくれます。発酵食品の栄養素の素晴らしさを伝える代表的な例として、江戸時代は夏に甘酒を売っていたという話があります。
今は甘酒は冬に飲むイメージですが、江戸時代はなぜ夏だったのか。その理由は、その時代の栄養ドリンクだったからだそうです。甘酒は米を原料としていますが、米のたんぱく質が発酵されると、ブドウ糖、アミノ酸に分解されます。この2つとも疲れをとってくれる大切な栄養素というわけなんですね。
そこで、小泉博士が甘酒を「飲む点滴」と言ったところ、多くの人が使い始めたらしいですよ。

1時間の講義はあっという間! もっと話しを聞いていたかったですね。小泉博士が最後に教えてくれたのは、体にいいものを食べたいなら和食ということ。

和食の基本の形は一汁三菜と言われ、発酵食品である味噌を使った味噌汁、発酵食品の漬け物というように、2つの発酵食品が入っています。だから体にいいんですね。和食が気軽に食べられる環境に生まれてよかった、と改めて実感した講義でした。小泉博士の話がもっと知りたいと思った方は丸ごと小泉武夫食マガジンをご覧ください。
次回は、発酵食品フェアに出店していたお店の紹介です。お楽しみに!