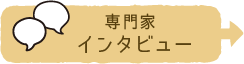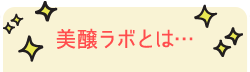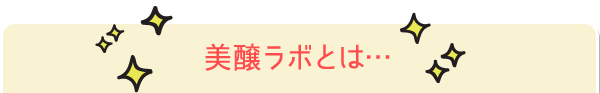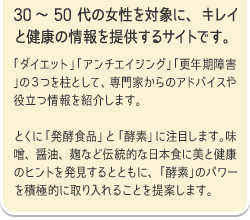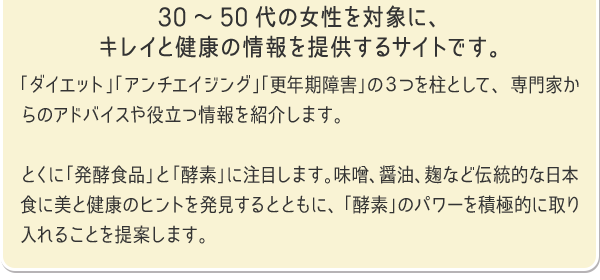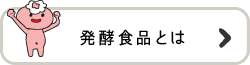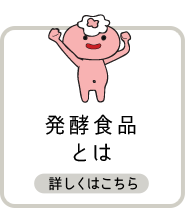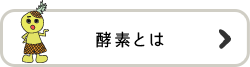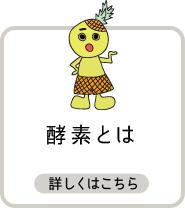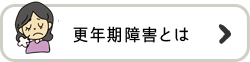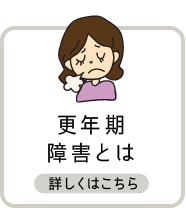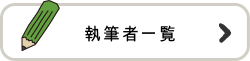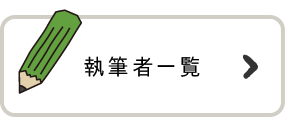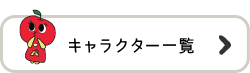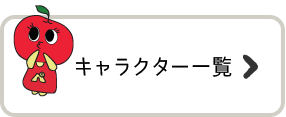和菓子の「くずもち」には、「くず餅」と「葛餅」の2種類あることをご存知でしょうか?どちらもひんやり冷やして夏に食べたい涼菓ですが、くず餅と葛餅はまったく別の食べ物です。
この記事では、日々さまざまな食べ物に興味を持ちながら料理を作る管理栄養士が、くず餅について詳しく解説します。くず餅とほかのよく似た和菓子との違いや、葛餅の作り方についてもご紹介します。くず餅について理解を深め、日本の伝統的な和菓子を身近に感じてください。
目次
発酵スイーツ、くず餅(久寿餅)とは?

くず餅とは、乳白色の見た目とぷるんとした弾力、歯切れのよさが特徴の和菓子です。味わいは淡白ですが、乳酸菌のはたらきを利用した発酵食品であるため、ヨーグルトを思わせるほのかな酸味があります。きな粉や黒蜜をかけるのが、一般的な食べ方です。
ここでは、くず餅の魅力についてさらに詳しく迫ります。
くず餅の原材料と作り方
くず餅の原材料は、いわゆる「うき粉」と呼ばれる小麦のでんぷんです。小麦でんぷんを水と合わせて1年ほど置き、乳酸発酵させます。発酵後、でんぷんを何度も水洗いして発酵臭を取り除き、加熱してとろみを付けます。型に流して蒸し上げると、くず餅の完成です。
小麦でんぷんは、1年半や2年もの長期間にわたって発酵させることもあります。十分に発酵した小麦でんぷんは強い臭いを放ちますが、この発酵臭は水洗いするとなくなります。この発酵が、くず餅特有の食感を作るのです。
くず餅の由来

くず餅は、関東地方発祥の和菓子です。「久寿餅」と表記され、江戸時代から庶民の味として親しまれてきました。
「くず餅」といえば、「葛餅」と表記する和菓子も知られていますが、この両者はまったく別の食べ物です。葛餅は、マメ科のつる草である葛の根から精製したでんぷんを原料に使用しています。一方、くず餅の原料は小麦でんぷんです。それにもかかわらず「くず餅」と名付けられた理由は、諸説あります。
かつて小麦の生産が盛んであった「下総国葛飾郡」では、農家の人々が小麦粉からお菓子を作って食べていました。そのお菓子は、地名から「葛」の漢字をとって「葛餅」と呼ばれるようになりました。しかし葛を使った「葛餅」がすでに存在していたため、それと区別するために「くず餅」や「久寿餅」と表記するようになった、といわれています。
別の説では、くず餅は久兵衛という人が作ったとされています。久兵衛は、雨に濡れてしまった小麦粉をこねて放置していました。食糧不足の折に久兵衛はそのことを思い出し、蒸してみるとおいしく食べられました。その食べ物が、久兵衛の「久」と無病息災を願う「寿」という漢字を組み合わせて「久寿餅」と呼ばれるようになったのです。
かつては一般的に広く食べられていた食べ物ですが、昔ながらのくず餅を作っている和菓子店は現在、数店しか残っていません。
くず餅の効果

くず餅に豊富な乳酸菌には、腸内環境を整える効果が期待できます。
人の腸内にはおよそ1,000種類、100兆個もの細菌が生息しているといわれています。これらの細菌は、善玉菌、悪玉菌、どちらにも属さない日和見菌に分けられ、それぞれがバランスを取り合いながら生存しているのです。
しかし偏った食事や不規則な生活、ストレスなどが続くと、悪玉菌が増殖します。腸内細菌のバランスが崩れると、便秘や下痢になりがちです。また、肌荒れや免疫力の低下をまねくおそれもあります。
食品から摂取した乳酸菌は、腸まで生きて届くと善玉菌になり、腸内環境の改善に活躍します。死滅した乳酸菌も、腸内細菌のエサになって善玉菌を増やすため、無駄にはなりません。
乳酸発酵した小麦でんぷんから作られているくず餅は、乳酸菌を豊富に含んでいます。そのため、くず餅を食べると腸内環境を改善できるでしょう。
オススメ記事
日本発酵食品の歴史と特徴をご紹介します。歴史や地域別の味噌・醤油の違いなど、日本の発酵文化を幅広く解説。世界の興味深い食品や、簡単に作れるレシピまで、身近な発酵食品の奥深さにハマること間違いなしです。

くず餅、葛餅、わらび餅、くずきりの違い

くず餅と同じ名前の葛餅、さらにわらび餅とくずきりは、よく似た食べ物です。ここでは、これら4種類の和菓子の違いを解説します。
くず餅と葛餅の違い

くず餅と葛餅100gあたりに含まれる主な栄養素は、以下のとおりです。
| くず餅 | 葛餅餅 | |
|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 94 | 93 |
| たんぱく質(g) | 0.1 | 0.1 |
| 脂質(g) | 0.1 | 0.1 |
| 糖質(g) | 22.4 | 22.5 |
小麦でんぷんを発酵させて作るくず餅と、葛の根のでんぷんから作られる葛餅。原料になる植物は異なりますが、どちらもでんぷんがもとになるため、栄養価はほぼ同じです。でんぷんとは、糖質がいくつもつながった物質のことです。そのためくず餅と葛餅は、どちらも糖質を豊富に含んでいます。
くず餅と葛餅の大きな違いは、見た目と食感にあります。くず餅は不透明な乳白色をしていますが、葛餅は半透明です。くず餅を食べると弾力と歯切れのよさを感じる一方、葛餅は口当たりがつるりとなめらかで、みずみずしくもっちりとした食感を楽しめます。
味わいはどちらもあっさりしていますが、葛餅は砂糖を加えて作られることが多いため、そのまま食べるとほんのり甘みを感じます。くず餅は乳酸発酵に由来する、かすかな酸味が特徴です。
わらび餅、くずきりとの違い

くず餅とわらび餅、くずきりの特徴を比較した表は、以下のとおりです。
| くず餅 | わらび餅 | くずきり | |
|---|---|---|---|
| 原料 | 小麦でんぷん | わらびでんぷん (じゃがいも、れんこんでんぷん) | 葛でんぷん |
| 見た目 | 乳白色で不透明 | 黒っぽく半透明 (白っぽく半透明) | 白っぽく半透明 |
| 食感 | 歯切れよく弾力がある | もっちりしてコシがある とろりとした口当たり | もちもち噛みごたえがある つるんとした口当たり |
| 味 | あっさり ほのかな酸味 | あっさり | あっさり |
くず餅とわらび餅、くずきりは原料に使用される植物が異なるほか、見た目や食感にも違いがあります。
古来から伝わるわらび餅の原料は、山菜で知られるわらびの根のでんぷんです。しかしわらびの根からでんぷんを取り出す工程は手間が掛かるうえ、量もわずかしか取れません。そのため現在は、じゃがいもやれんこんのでんぷんを使用することが通例です。
わらびでんぷんから作られたわらび餅は、黒やグレーのような色をしています。一方、じゃがいもやれんこんのでんぷんを使用したわらび餅は、白っぽく透明感があります。
くずきりの原料は、葛餅と同じ葛の根のでんぷんです。くずきりは形状が独特で、麺のように細長くカットして食べられます。つるりとした口当たりやのど越しが、くずきりの魅力です。
葛餅の作り方

くず餅は手間と時間がかかる発酵食品であるため、家庭で手作りするのは簡単ではありません。そこで今回は、手軽に作れる葛餅のレシピを紹介します。
材料(3人分)
- 本葛粉
- 50g
- 砂糖
- 15g
- 水
- 200ml
- きな粉
- 適量
- <黒蜜>
黒砂糖 - 100g
- 水
- 50ml
作り方
- 鍋に<黒蜜>の材料を入れて、混ぜながら中火にかけて黒砂糖を溶かす。とろみがつくまで煮詰めたら、茶こしでこして冷ます。
- 別の鍋に本葛粉、砂糖、水を加え、混ぜ合わせて粉をよく溶かす。
- 中火にかけながら葛餅を練り上げる。全体が透明になったら、さらに1〜2分ほど練り、火を止める。
- 水で濡らしたバットなどの型に3を流し入れ、型ごと氷水に入れて冷ます。
- 冷えて固まったら型から取り出し、食べやすい大きさにカットする。器に盛りつけて、きな粉と黒蜜をかける。
火にかける前に、本葛粉を水にきちんと溶かしましょう。加熱をはじめたら絶えずよく混ぜて、葛餅を焦がさないようにしてください。型を水で濡らしておくと葛餅がくっつかず、取り出しやすくなります。
葛餅は冷蔵庫で保存すると硬くなり、透明感が失われてしまうため、作りたてを食べるようにしてください。
爽やかなおやつタイムにおすすめアレンジレシピ

普通の葛餅に飽きてきたら、アレンジして楽しんでみませんか?ここでは、葛餅のアレンジレシピを紹介します。
抹茶葛餅
抹茶を練り込んだ葛餅に、ゆであずきを添えたレシピです。抹茶がダマにならないよう、あらかじめ砂糖と混ぜ合わせること、一度こすことがポイントです。抹茶の鮮やかな色と清々しい香り、かすかなほろ苦さが楽しめます。
材料(3人分)
- 本葛粉
- 50g
- 抹茶
- 5g
- 砂糖
- 15g
- 水
- 200ml
- ゆであずき
- 適量
作り方
- ボウルに抹茶と砂糖を入れて、よく混ぜ合わせる。
- 1に本葛粉と水を加え、混ぜ合わせる。粉が溶けたら、こしながら鍋に移す。
- 中火にかけながら葛餅を練り上げる。全体が透明になってから、さらに1〜2分ほど練り、火を止める。
- 水で濡らしたバットなどの型に3を流し入れ、型ごと氷水に入れて冷ます。
- 冷えて固まったら型から取り出し、食べやすい大きさにカットする。器に盛りつけて、ゆであずきを添える。
ブルーベリーソースの葛餅
葛餅は和菓子ですが、洋風のブルーベリーソースもよく合います。ソースはフルーツジャムを使うので、手軽に作れます。好みのジャムを使用して、アレンジを楽しんでください。
材料(3人分)
- 本葛粉
- 50g
- 砂糖
- 15g
- 水
- 200ml
- きな粉
- 適量
- <ブルーベリーソース>
ブルーベリージャム - 90g
- 水
- 30ml
作り方
- 鍋に<ブルーベリーソース>の材料を入れて、混ぜながら弱火で加熱する。全体がなじんだら、火を止めて冷ます。
- 別の鍋に本葛粉、砂糖、水を加え、混ぜ合わせて粉をよく溶かす。
- 中火にかけながら葛餅を練り上げる。全体が透明になってから、さらに1〜2分ほど練り、火を止める。
- 水で濡らしたバットなどの型に3を流し入れ、型ごと氷水に入れて冷ます。
- 冷えて固まったら型から取り出し、食べやすい大きさにカットする。器に盛りつけて、ブルーベリーソースをかける。
オススメ記事
【永久保存版】甘酒の知られざる効果とは?デメリットも合わせて解説
甘酒の効果解説を徹底解説。美容と健康に優しい日本の伝統的な飲み物の、甘酒の魅力と効果を解説します。また飲み方や人気ブランドまで、完全に情報を網羅してみました。日常に取り入れて健康な生活を始めてください。

伝統の発酵和菓子「くず餅」を食べてみよう

くず餅とは、小麦でんぷんを長期間発酵させて作る、関東地方発祥の和菓子です。乳白色の外観、ぷるんとした弾力と歯切れのよい食感が特徴です。味わいはあっさりしており、かすかな酸味を感じます。また、乳酸菌が含まれているため整腸作用が期待できます。
くず餅とよく似た食べ物に葛餅やわらび餅、くずきりがありますが、これらはまったく別物です。葛餅とくずきりは葛のでんぷん、わらび餅はわらびのでんぷんから作られます。見た目や食感も、くず餅とは異なります。
家庭で作るなら、葛餅がおすすめです。この記事で紹介した基本の作り方やアレンジレシピを参考にして、日本の伝統的な和菓子を作ってみてください。
【参考文献】
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
厚生労働省 e-ヘルスネット「腸内細菌と健康」