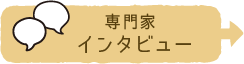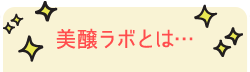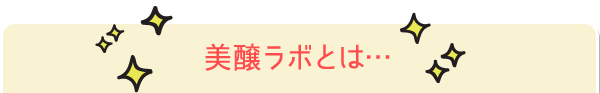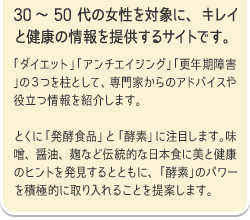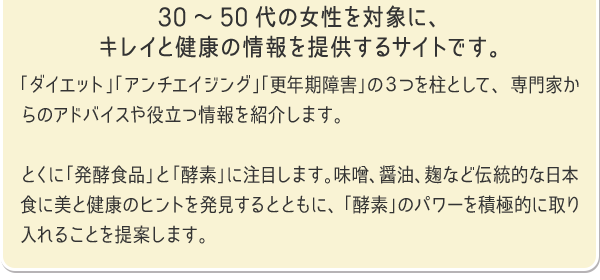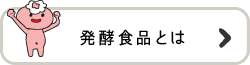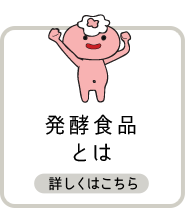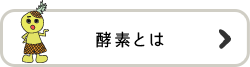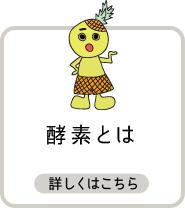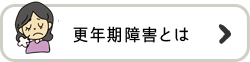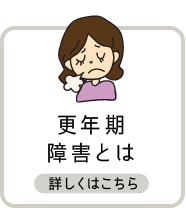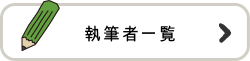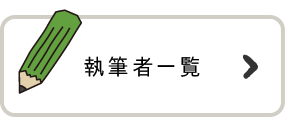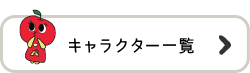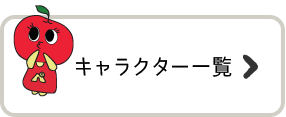甘酒は、減糖志向や健康美容への関心の高い方にぴったりの飲みものです。
2016年の末頃の空前のブームから流行が続き、現在は発酵飲料として定番といえるでしょう。
スーパーでもさまざまな種類の甘酒が、豊富に取り揃えられているのを目にします。
糀甘酒からフレーバー豊かな甘酒まで、たくさんの種類があり、選ぶ楽しさもあるでしょう。
さらに、米麹を使った甘酒は、自宅でも手軽に作れるのでますます人気です。
自家製甘酒は、添加物を気にせず、好みの甘さや風味にアレンジが可能ですよ。
栄養豊富な健康飲料として、子どもや家族、友だちと一緒に楽しむこともできます。
目次
甘酒は2種類:米麹か酒粕から作る!

甘酒は2つの種類があります。
1つは米麹を使って作るもので、もう1つは酒粕を使って作るものです。
それぞれ、味や香りに違いがあります。
米麹を使った甘酒
米麹を使った甘酒は、米と麹を主原料とし水と一緒に発酵させることで作られます。
この甘酒は、まろやかな味わいと穏やかな甘さが特徴です。
米麹由来の甘みが広がり、温かくても冷やしても楽しむことができます。
アルコールを含まないため、さっぱりとした口当たりです。
暑い季節にぴったりで、爽やかな飲みごたえを味わうことができます。
酒粕を使った甘酒
酒造りの際に残る酒粕を主原料として、水や砂糖と一緒に煮出して作る甘酒です。
酒粕は日本酒の醸造過程で残る発酵した米の「かす」なので、米麹を使った甘酒に比べると、より濃厚な味わいと独特の香りが楽しめます。
ただし、アルコールが含まれている場合があるため、お子さまやお酒に弱い方は注意しましょう。
甘さと酸味のバランスがよい点も酒粕甘酒の特徴です。
酒粕には糖分が含まれており、発酵の過程で酸味も生じるため、甘さと酸味が絶妙なバランスで調和しています。
酒粕を使った甘酒はその濃厚な味わいと風味から、飲みごたえのある口当たりが楽しめます。
一口飲むだけで満足感を得ることができ、じっくりと味わいながら飲むことができるでしょう。
甘酒は江戸時代の栄養ドリンク

甘酒は江戸時代から栄養ドリンクとして親しまれてきました。
その当時、甘酒は一般的な飲み物として広く飲まれており、暑い夏には体力補給のための飲み物としても人気でした。
農村部では、炊きたてのご飯を使用して作られることが多く、とくに農家の人々に愛されていたようです。
砂糖が一般的ではなかった時代において、甘酒は貴重な甘味を楽しむ飲み物として重要でした。
当時の人々は、甘酒の栄養価や美容効果については現代よりも限られた理解しか持っていなかったようです。
しかし、そのおいしさと健康への良さは幅広く認知されていました。
現在では、科学の進歩によって甘酒の栄養価や効果がより明確になり、その優れた栄養成分と美容効果が高く評価されています。
甘酒の美容効果と栄養成分

甘酒は美容や健康に嬉しい栄養成分が豊富に含まれています。
以下に代表的な栄養成分とその効果をご紹介します。
ビタミンB群
肌や髪の健康を保ち、新陳代謝を促進。
肌のくすみを防いだり、肌荒れを改善したりする効果を期待できます。
アミノ酸
コラーゲンの生成を促進し、肌のハリや弾力を保ちます。
肌の乾燥を防ぎ、潤いをキープする効果も。
食物繊維
腸内環境を整えるので、便秘の予防、解消効果があります。
腸内の善玉菌を増やすので、美肌効果も期待できますよ。
オリザノール
玄米甘酒に含まれている、玄米由来の成分です。
血液循環を促進。血流が良くなることで、肌のターンオーバーを促進し、くすみの改善に役立ちます。
フェルラ酸
抗酸化作用があり、紫外線やストレスから肌を守る効果があります。
シミやシワの予防にも効果的です。
オススメ記事
発酵食品は食べ過ぎ注意!知っておきたいデメリットと効果的な食べ方とは
健康に良い発酵食品も、食べ過ぎると悪影響になってしまいます。発酵食品を普段から取り入れている管理栄養士がデメリットを解説し、適切な量と食べ方をお伝えします。さらに、食卓にちょこっとプラスできる簡単健康レシピもご紹介します。

簡単手作り甘酒!米と麹で作るおいしい方法

ごはんと麹を使った家庭でできる、簡単な甘酒の作り方をご紹介します。保温の機材として、炊飯器を利用したレシピです。放っておいてもできるので、手軽に作れますよ。
材料
- 炊いたご飯
- 3合
- 米麹
- 300g
- 水
- 400ml
準備するもの
- 炊飯器(または鍋)
- 布巾
- 保存用タッパーまたは冷凍保存袋
作り方
- 炊いたご飯が熱いうちに、水400mlを加えて混ぜます。

- ご飯の温度が約60度になるまでかき混ぜながら冷まします。炊飯器を使用する場合、お釜を取り出して冷ますと早く温度が下がりますよ。

- 米麹を加えてよく混ぜます。
- 炊飯器の保温モードにし、蓋を開けた状態で布巾をかぶせ、約13時間保温します。

- 2〜3時間後に一度かき混ぜます。
- その後、2〜3回に分けてさらにかき混ぜます。
- 甘酒が完成したらスイッチを切り、粗熱が取れるまでそのままにします。
保管
完成した甘酒は適切な方法で保管しましょう。
- 冷蔵保存
清潔な密閉容器に甘酒を移し替えて冷蔵庫に保管します。
- 冷凍保存
長期間保存する場合は、冷凍保管がおすすめです。
甘酒を完全に冷ましてから、冷凍に適した容器や製氷皿に注ぎ、密閉してラップをかけて冷凍庫に置きます。
甘酒を飲むときに、冷蔵庫で解凍するか、電子レンジで軽く温めて好みの温度にしましょう。
時間
作り始めから甘酒が飲めるようになるまでの時間:約1日半
費用
手作り甘酒の費用は、麹や米の価格、追加の材料、電気代などの価格によって変わります。
一般的には市販の麹は約900円/1000g、米の価格は約270円/750g程度です。
また、甘酒作りには保温時間が必要ですが、マイコン炊飯器の場合、13時間の保温には約6.63円、IH炊飯器の場合は約4.94円の電気代がかかるといわれています。
これらの価格を考えると、手作り甘酒は市販のものに比べて安く、経済的なことが多いです。
温度管理について
米と麹を使った手作りの甘酒を作る際の温度管理に重要なポイントは、温度を55〜60℃の間で保つことです。
この温度範囲を保つことが、甘酒作り成功のコツといえるでしょう。
温度が低すぎると発酵が進まず、甘みが足りなくなる可能性があります。
逆に高すぎる温度は麹菌に悪影響を及ぼすことがあるので、気をつけましょう。
炊飯器以外にも、ポットや魔法瓶などの保温機能で温度管理することが可能です。
それらの機材を使用する場合でも、可能であれば温度計を利用して定期的に温度を確認することがおすすめです。
一般的な方法としては、温度を55℃〜60℃に保ちつつ、約6時間ほど保温する方法が良く使われています。
ただし、温度管理が難しい場合には、保温時間を長めに調整することでも発酵を進めることが可能です。
米と麹の甘さと栄養を満喫!甘酒のアレンジレシピ
甘酒のアレンジとして最もおすすめは、そのまま甘味料として活用することです。
砂糖はカロリーがある一方で、栄養価はほとんど期待できません。
しかし、同じ甘さを求めるのであれば、甘酒を砂糖の代わりにすることで、栄養価もプラスされるメリットがあります。
以下に、甘味料として利用する以外の甘酒を使ったおすすめレシピをご紹介します。
どちらも簡単アレンジレシピなのでぜひ作ってみてくださいね。
やさしい甘みの甘酒パンケーキ

甘酒パンケーキは、まろやかな甘さが特徴。甘酒の自然な甘みがほんのり香る、
やさしい味わいのパンケーキです。ふんわりとした食感と穏やかな甘みが楽しめます。
朝食やスイーツとして、どんなシーンでも楽しめる一品です。
材料(2人分)
- 薄力粉
- 120ml
- ベーキングパウダー
- 大さじ1
- 塩
- 1/4小さじ
- 甘酒
- 120ml
- 牛乳
- 120ml
- 卵
- 1個
- サラダ油
- 大さじ2
作り方
- 薄力粉、ベーキングパウダー、塩を大きなボウルに混ぜ合わせます。
- 別のボウルで甘酒、牛乳、卵、サラダ油をよく混ぜます。
- 2を3に入れ、よく混ぜ合わせます。
- 中火で加熱したフライパンに、1/4カップずつの生地を流し入れます。
- 4の表面に小さな泡が立ったら、裏返して焼きます。
- 両面がきつね色になるまで焼いたらできあがり。
ひんやり甘酒スムージ

甘酒スムージーは、栄養価がとても豊富で、爽やかな味わいが楽しめます。朝食やおやつにもぴったり。
暑い季節に飲むと、気分もリフレッシュできますよ。
材料(1人分)
- 甘酒
- 240ml
- バナナ
- 1本(凍らせておく)
- そのほか果物(ベリー・りんご・カットマンゴーなどお好みで)
- 適量
- ヨーグルト
- 60ml
- 蜂蜜やシナモン(お好みで)
作り方
- 全ての材料をミキサーに入れます。
- 1をクリーミーになるまでミキシングして、グラスに注いでできあがり。
米と麹でつくる甘酒で輝く私を目指そう♡

甘酒は、減糖志向や健康や美容への意識の高まりによって、大きな注目を浴びています。
自宅で手軽に作れる米と麹を使用した甘酒も、ますます人気です。
自家製の甘酒は、不要な添加物を気にすることなく、自分の好みに合わせた甘さや風味を楽しむことができますよ。
その豊かな栄養価は、健康や美容への効果も期待できるでしょう。
飲むだけでなく幅広い活用法を通じても、甘酒の素晴らしさを実感できますよ。
美と健康を手にするために、ぜひ甘酒を取り入れてみましょう。
オススメ記事
発酵食品を摂りすぎるとどうなるの?失敗しない1日の摂取量とデメリット
発酵食品を摂りすぎると体調不良になる?そうならないために、発酵食品適切な摂取量と効果を解説します。摂り過ぎるとお腹の不調やむくみ、高血圧、高血糖のリスクの原因に。バランスのとれた食生活を送るための献立もご紹介します。