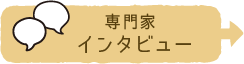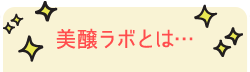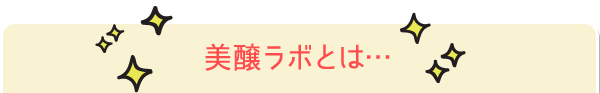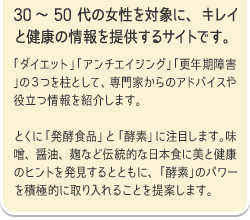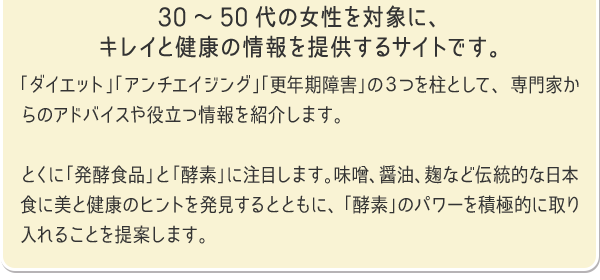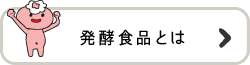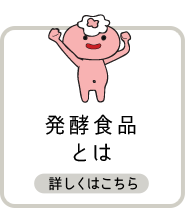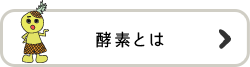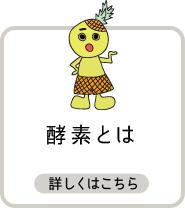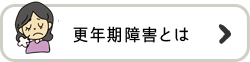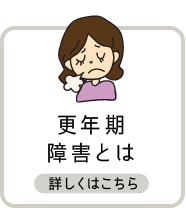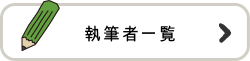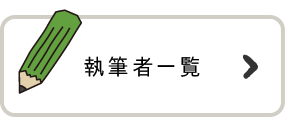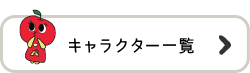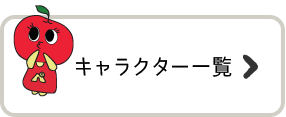甘酒は健康や美容にいい栄養素がたっぷりの発酵食品です。
発酵食品を健康や美容に活かすには毎日継続的に食習慣に取り入れることが欠かせません。
甘酒を手作りすることで継続的に発酵食品を食習慣に取り入れやすい環境を作りましょう。
この記事では自宅での甘酒の作り方を解説していきます。
甘酒は色々な作り方で作ることができるので自分に合った作り方を見つけてくださいね。
目次
甘酒を自分で作ることのメリット

市販の甘酒は保存性を高めるために、発酵完了後に火入れを行っているものが多いです。
火入れを行うことで発酵が止まるので保存性は高まりますが、菌類を熱で止めてしまうことで栄養価が火入れ前のものよりも少なくなってしまいます。
以上の理由から、甘酒の栄養をまるごと取り入れるには手作りがおすすめです。
甘酒を作る前に知っておきたい麹と甘酒の種類とは?

甘酒を作る前に、甘酒にはいくつか種類があることを知識として取り入れておきましょう。
甘酒には大きく米麹甘酒と酒麹甘酒に分類することが出来ます。
| 甘酒 | 米麹甘酒 | 酒粕甘酒 |
|---|---|---|
| 原料 | 米麹 | 酒粕 |
| アルコール | 含まれない | 1~2%含まれる |
| 特徴的な栄養素 | ビオチン (肌荒れや肌のくすみ改善に効果がある) | レジスタントプロテイン(油を排泄する成分) |
米麹甘酒
甘酒の中でも最もポピュラーな米麹で作られた甘酒です。
クセがなく飲みやすいのが特徴で、温めても冷やしても美味しく飲むことが出来ます。
玄米麹甘酒
玄米麹で作られた甘酒です。
米麹で作られた甘酒よりも色合いが濃く、玄米特有のつぶつぶとした食感があることが特徴です。
米麹よりも食物繊維が豊富なので糖の吸収を穏やかにする作用、腸内環境を整える作用があります。
黒麹甘酒
黒麹で作られた甘酒です。炭のように黒い色が特徴で、クエン酸が含まれるため酸っぱい味がします。甘い味が苦手な方やクエン酸による疲労回復効果を期待する人におすすめの甘酒です。
紅麹甘酒
紅麹(べにこうじ)甘酒とは、紅麹で作られた甘酒で、うすい小豆色をしており、フルーティな味わいが特徴です。
紅麹は発酵の過程でGABAやモナコリンKという物質を生み出します。
GABAは血圧を下げる効果があり、モナコリンKにはLDLコレステロールの体内産生を阻害する効果があります。
オススメ記事
【永久保存版】甘酒の知られざる効果とは?デメリットも合わせて解説
甘酒の効果解説を徹底解説。美容と健康に優しい日本の伝統的な飲み物の、甘酒の魅力と効果を解説します。また飲み方や人気ブランドまで、完全に情報を網羅してみました。日常に取り入れて健康な生活を始めてください。

甘酒を炊飯器で作る方法

みなさんのご家庭にある炊飯器の保温モードを使用して甘酒を作ることができます。
調理時間の目安:約9時間
材料
- 米麹
- 2カップ
- ご飯(炊いたもの)
- 2カップ
- お湯(60~70℃くらい)
- 4カップ
作り方
- 炊飯器に【材料】を加えて混ぜたら保温モードにします。

- 2時間おきくらいにかき混ぜながら約9時間保温します。
- 味見をして、好みの甘さになったら甘酒の完成です。
甘酒をヨーグルトメーカーで作る方法

ヨーグルトメーカーを使って米麹とお湯だけで甘酒を作る方法をご紹介します。
ヨーグルトも甘酒も発酵食品です。発酵させることが得意な調理器具を使って楽に甘酒を手作りしてみましょう!
調理時間の目安:約6時間
材料
- 米麹
- お湯
作り方
- ヨーグルトメーカーの内容器を消毒します。
- 板状の米麹を使用する場合は米麹をバラバラにします。
- 鍋でお湯を沸かします。温度計を使用して62〜63℃になるようにしましょう。
- 米麹とお湯を米麹の塊が残らないようによく混ぜます。
- 内容器をヨーグルトメーカーにセットします。60℃6時間に設定をしたら発酵スタートです。この後は発酵終了まで待つのみです。
- 6時間後に味見をして甘味が出ていたら甘酒の完成です。
- 保存:消毒した容器に出来上がった甘酒を移し、冷蔵庫で保管します。
甘酒をホームベーカリーで作る方法

ホームベーカリーはパン以外にも、ヨーグルトやフレッシュチーズを作る事のできる多機能なものが多く販売されています。
ホームベーカリーも発酵食品を扱うことが得意な調理家電です。
ここではヨーグルトを作る機能がついているホームベーカリーを利用する甘酒の作り方を紹介します。
調理時間の目安:約6時間
材料
- 米麹
- 100g
- 湯(65℃)
- 120ml程度
作り方
- ホームベーカリーの容器を殺菌します。
- 65℃前後のお湯を用意します。
- 容器に100gの米麹と②をよく混ぜ合わせます。
※混ぜ合わせる時に使うスプーンなどの道具も消毒してから使いましょう。 - ホームベーカリーに容器をセットしてヨーグルトモードで発酵を開始させます。
- 約6時間で甘酒が完成します。2時間おきくらいに消毒したスプーンでよく混ぜることで均一に発酵をすすめることができます。
甘酒を魔法瓶で作る方法

ここまでは電気調理器を使用しての甘酒の作り方を紹介してきましたが、魔法瓶を使って甘酒を作れば電気を使わずに発酵をすすめることができるので環境にも優しい作り方です。 ちょうどいいサイズの魔法瓶がご自宅にある場合は挑戦してみてくださいね。
調理時間の目安:約8時間
材料
- 米麹
- 250g
- 水
- 300cc
- ※米麹の重量に対して水の量は1.2倍です。ご自宅にある魔法瓶のサイズに合わせて量を調整してみてくださいね
作り方
- 鍋に水を入れてお湯を沸かします。お湯の温度は65℃くらいまであげましょう。
- ①の鍋に火を止めた状態で米麹を入れます。
- よく混ぜてから火を入れて65℃まで加熱します。加熱のし過ぎに注意してください。
- 魔法瓶を予めお湯で温めておきます。
- 魔法瓶を温めておくためにいれておいたお湯を捨てて③を魔法瓶に入れます。
- 蓋をして4時間待ちます。
- 魔法瓶の中の温度を確認します。60℃以下まで温度が下がっていた場合は再度鍋に入れて65℃前後まで温度をあげます。
- ⑦を再度魔法瓶に移し4時間寝かせます。計8時間後には美味しい甘酒が出来ています。
※魔法瓶や鍋などの調理器具は消毒・殺菌をしてから使用しましょう。
甘酒を麹だけで作る方法

お粥を炊かずに炊飯器で時短で甘酒造りをしたい時に便利な作り方です。
調理時間の目安:約6〜8時間
材料(五合炊き炊飯器)
- 米麹
- 400g
- 湯
- 800cc
- 水
- 200cc
作り方
- 炊飯器の保温スイッチを入れます。
- 湯を800cc沸かして内釜に入れて冷水を入れて温度を下げます。(65℃くらいが目安です)
- バラバラにほぐした麹を入れて混ぜます。
- 炊飯器の蓋は開けたままで濡れた布巾をかけて6~8時間発酵させます。
- 3時間後に消毒したヘラでかき混ぜます。
- 6時間後、味見をして甘味が出ていたら完成です。甘みが足りなかったり、麹が硬い場合はこのまま発酵2時間ほど延長しましょう。(使用する麹の状態によって発酵時間は変わります。)
甘酒を米と麹で作る方法

甘酒は残りご飯や冷凍ご飯、雑穀ごはんや麦ごはんでも炊飯器を使用して作ることができます。
調理時間の目安:約6〜8時間
材料
- 米麹
- 200g
- 好みのご飯
- 200~300g
- 湯
- 300~400ml
- 水
- 200〜300ml
作り方
- 炊飯器にご飯とお湯を入れて蓋をして炊飯か早炊きで加熱をします。蒸気口から蒸気が出てきたらすぐに取り消しボタンを押しましょう。
- ご飯がお粥くらいの柔らかさになっていると思います。保温で加熱が続かないように気をつけてくださいね。
- 65℃くらいまで水を加えて温度を下げます。なかなか冷めない場合は氷を少しずつ加えましょう。一気にたくさんの氷を入れてしまうと温度が下がりすぎてしまうので温度を測りながら慎重に調整しましょう。
- 65℃まで下がったら米麹加えてよく混ぜます。
- 蓋を開けたままで保温にし、濡れ布巾をかけます。
- 2時間おきくらいで撹拌をします。6~8時間程度で味見をして甘さが出ていたら完成です。
甘酒を餅米を使って作る方法

餅米を使用して作った甘酒は白米を使用して作った甘酒と比較して甘味が強く、もっちりとした食感が特徴です。
調理時間の目安:約6〜8時間
材料
- 米麹
- 300g
- 餅米
- 一合
- 水
- 500cc
- 塩
- ひとつまみ
作り方
- 餅米1合を炊飯器のおかゆモードで炊きます。
- 炊きあがったら水を加えて温度を65℃くらいまで下げます。
- ②に米麹を加えてよく混ぜます。
- 炊飯器の蓋を開けたまま保温モードにして濡れた布巾をかけます。
- そのまま6~8時間程度発酵させます。2時間おきくらいにヘラでかき混ぜましょう。
※麹の状態によって発酵時間が変化します。味見をして甘味が出ていたら完成です。
オススメ記事
日本発酵食品の歴史と特徴をご紹介します。歴史や地域別の味噌・醤油の違いなど、日本の発酵文化を幅広く解説。世界の興味深い食品や、簡単に作れるレシピまで、身近な発酵食品の奥深さにハマること間違いなしです。

酒粕を使った甘酒の作り方

酒粕を使った甘酒の作り方を紹介します。酒粕を使用した甘酒にはレジスタントプロテインという油を排出する栄養素が含まれているのが特徴です。
健康や美容に甘酒を取り入れたい時に米麹甘酒と酒粕甘酒を使い分けることができるとより効果的です。米麹甘酒よりも短時間で作ることができるのも酒粕甘酒の魅力です。
調理時間の目安:約10分
材料 一人前(250ml)
- お湯
- 200ml
- 酒粕
- 30g
- 砂糖
- 大さじ1
作り方
- 酒粕は一口大にちぎります。
- 鍋にお湯を強火でかけます。沸騰したら①を入れて全体になじませ、火からおろします。
- 酒粕が溶けたら強火にし、砂糖を入れて全体が馴染むように混ぜて火からおろします。
- 最後に、カップに注いで出来上がりです。生姜やお好みのスパイスを加えても美味しく飲むことができます。
甘酒を使った簡単レシピ

甘酒のは砂糖の代替として使用することができます。料理に発酵食品を取り入れたいと思っている人や甘酒を作りすぎてしまった人は是非お料理にも甘酒を活用してみてください。
鶏肉の甘酒煮

調理時間の目安:約20分
材料
- 手羽元
- 10本
- ☆だし汁
- 600cc
- ☆料理酒
- 大さじ1
- ☆甘酒
- 180g
- ☆みりん
- 大さじ1
- ☆醤油
- 大さじ3
作り方
- ☆を合わせて鍋でひと煮立ちさせます。
- ①に手羽元を加えます。
- 中火で落し蓋をして10分、落し蓋を外して10分程度煮込みます。
※甘酒の米粒が気になる方はすりこぎやフードプロセッサーを使用してつぶつぶをなめらかにしてから使用するといいですよ。
甘酒卵焼き

砂糖の代わりに甘酒を使用した卵焼きです。自然な甘さが卵焼きの美味しさを引き立ててくれますよ。
調理時間の目安:約5分
材料
- 米麹甘酒
- 大さじ2
- 卵
- 3個
- 白だし
- 大さじ1
- サラダ油
- 適量
作り方
- 卵をボウルに入れて溶きます。
- 米麹甘酒と白だしを入れて混ぜます。
- 卵焼き器にサラダ油をひき、よく温めてから卵焼きを焼きます。
甘酒を美味しく保管する方法

甘酒は冷蔵でも冷凍でも保存することが可能です。
それぞれの保存方法を紹介しますのでたくさん作りすぎてしまった場合に適した保存方法を選択していつでも手作りの甘酒を楽しみましょう!
冷蔵庫を使用した保存方法
| 米麹甘酒 | 酒粕甘酒 | |
|---|---|---|
| 火入れしていない場合 | 1週間 | 3日 |
| 火入れしている場合 | 3週間 | 1週間 |
酒粕甘酒は酒粕をお湯に溶かして作るだけで手軽に作ることが出来ますが、調理過程で水と混ぜるため保存期間は短くなってしまいます。
酒粕そのものは長く保存が効くので飲みたい分量ずつ作るのがおすすめです。
「火入れ」とは?
保存性を大きく高めるポイントは「火入れ」です。
火入れとは、完成した甘酒を一旦加熱して沸騰させることをいいます。火入れを行うことで雑菌の繁殖と活きた酵素の働きを止める事ができるので保存期間を伸ばすことができます。
保存性は高まりますが、発酵食品特有の酵素の働きも止まってしまいます。用途に合わせて「火入れ」をすることと、しないことを選択できるといいですね。
冷凍庫を使用した保存方法
冷凍保存の場合、2ヶ月ほど保存することが可能です。
また、冷凍された酵素は一時的に休眠状態になります。解凍することで酵素の働きは戻ってきます。
酵素の働きを損なわずに長期保管がしたい場合には、冷凍保存がおすすめです。
保存容器~発酵食品づくりのポイント
甘酒を安全に保存するために、菌の侵入を防げる密封可能なふたが付いた容器を使用しましょう。
また、しっかり洗浄し、熱湯で殺菌しておくことも雑菌の繁殖を防ぐ上で重要です。
甘酒は簡単お手軽に手作りしよう

この記事では甘酒の作り方をいくつか紹介しました。
ご自宅にある道具で挑戦できそうなものはありそうでしたか?
米麹甘酒を自宅で作るポイントは60℃前後でしっかり発酵させることです。市販の甘酒は長期保存が可能なように火入れしているものが多いです。活きている酵素を取り入れるには手作りするのがおすすめです。スーパーで手軽に買うことができる・少ない材料で作ることができることも嬉しいポイントです。
甘酒作りは発酵食品づくりの基本が詰まっています。これから発酵食品を手作りすることに挑戦したいと思っている人にはまずは甘酒を手作りしてみることをおすすめします。
何回か作ってみると自分好みの硬さや甘さ、粒感を調整する楽しみも出てきますよ。是非、ご自宅でチャレンジしてみてくださいね!
オススメ記事
発酵食品のメリット5選!驚くべき効果と効果的な摂取法もご紹介
発酵食品といえば納豆やヨーグルト、味噌など身近な食品が多いけど、メリットは浮かびますか?発酵食品のメリットは、免疫力向上、便秘改善、ストレス軽減、生活習慣病予防などたくさん。さらに注意しないと生じるデメリットもご紹介。